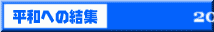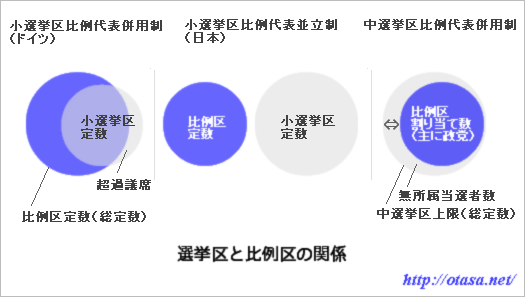小選挙区比例代表併用制の問題点
ドイツ下院の小選挙区比例代表<併用>制は、小選挙区制に反対する人の中でもかなり人気があります。確かに日本の現行制度である小選挙区比例代表<並立>制に比べれば、はるかに民意を反映できる選挙制度といえます。
しかし、ドイツの小選挙区比例代表併用制でも、無所属候補に不利な比例代表制の性格はそのままであるし、いわゆる「超過議席」(下で説明)を認めるために、小選挙区制の弊害を排除しきれていません。
下記文献を参考に、ドイツ型の小選挙区比例代表併用制の問題点を指摘しておきます。(印刷用ファイル)
共同声明「国会議員の定数削減に抗議する」賛同募集中
改訂:2009年11月22日
[参考文献]
渡辺洋三・森英樹・広渡清吾『政治改革への提言』(岩波ブックレットNO.291、1993年)
[関連記事]
小選挙区制の廃止へ向けて
http://kaze.fm/wordpress/?p=215
中選挙区比例代表併用制を提案する
http://kaze.fm/wordpress/?p=164
【目次】
(1) ドイツの小選挙区比例代表併用制とは?
(2) ドイツ型の小選挙区比例代表併用制は政党の優先枠を設定する(無所属候補に不利)
(3) ドイツでは個人を選びうる制度として小選挙区制を併用した
(4) 超過議席を認めるドイツ型の小選挙区比例代表併用制では小選挙区制の弊害を排除できない
(5) ドイツ型の小選挙区比例代表併用制でも小選挙区では大政党への投票を誘導する
ドイツ下院の小選挙区比例代表併用制は、大雑把にいえば、小選挙区制が組み込まれた比例代表制といえる。(仮)総定数は598で、その半数の299が小選挙区に割り当てられている。下図参照。
有権者は1人2票をもち、1票(第1投票)を小選挙区で候補者に、もう1票(第2投票)を政党が用意する候補者名簿に投ずる。政党名簿投票に基づき、(仮)総定数の598議席が比例配分されるが、小選挙区での当選者に優先配分される。小選挙区に割り当てられた議席が比例配分の対象にならない衆院の小選挙区比例代表<並立>制とは、この点が大きく異なる。小選挙区選挙での当選は、政党名簿投票の結果に関係なく、確定する。
例えば、A党の比例配分による議席割り当て数が30議席であるとする。小選挙区での当選者数が15人であれば、この15が30に繰り入れられ、A党の最終的な獲得議席数は30となる。この場合、政党名簿からの当選者は15人。一方、小選挙区での当選者数が35人であれば、最終的な獲得議席数は35となる。この場合、政党名簿からの当選者数はゼロ。
後者の例のように、小選挙区での当選者数が比例配分された議席割り当て数より大きい場合でも、その差が「超過議席」として認められる。だからドイツ型の小選挙区比例代表併用制は、厳密な比例代表制とはいえない。
(無所属候補に不利)
一般に比例代表制で無所属候補が当選することは難しい。ドイツ型の小選挙区比例代表併用制では、総定数から小選挙区の定数を差し引いた議席数が、ほぼ政党の独占枠になっている。この特性は、日本の小選挙区比例代表並立制と変わらない。無所属候補に不利な制度といえる。
小選挙区比例代表併用制の問題点というわけではないが、小選挙区制の特性を知る上で重要だと思うので、ドイツでの事例を紹介しておきたい。
日本では、小選挙区制の特性を政策本位・政党中心の選挙戦をもたらすものとされたが、ドイツでは、比例代表制では人物本位に選べないという批判に応えて、「個人を選びうる比例代表制」として、比例代表制に小選挙区制が併用されたという経緯がある。
CDU/CSUの小選挙区候補は、地域利害の代表を最も重視し、党の基本政策と異なる政策を掲げることも稀ではない。候補者の決定も、党中央の関与は小さいという(自由法曹団統一ドイツ選挙調査団『選挙制度と民主主義―統一ドイツ選挙調査報告』、1991年)。
小選挙区制の弊害を排除できない
超過議席の発生例としては、2009総選挙でCDU/CSUが24の超過議席を獲得した選挙が挙げられる。CDU/CSUは得票率が33.8%(前回比1.4%減)であるにもかかわらず、239議席(13増)を獲得し、議席獲得率は38.4%だった。
[参照]
ドイツの「政権交代」 —— 二大政党の退潮 2009年10月5日(水島朝穂、今週の「直言」)
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2009/1005.html
しかし超過議席数がその程度に収まるとは限らない。極端な例を考えてみる。3つの政党のみが候補者を立て、小選挙区すべてと政党名簿投票で、各党の得票率がほぼ同じ約3分の1とする。
各党の比例配分による議席割り当て数は(仮)総定数598の約3分の1だから、約199となる。政党Aが、他党よりも得票率がわずかに優勢で、小選挙区の299議席すべてを独占したとする。この場合、(A党による)超過議席は約100にも上る。
このように、小選挙区比例代表併用制であっても、超過議席を認めれば、得票率と議席獲得率の乖離を許すことになる。
小選挙区では大政党への投票を誘導する
政党名簿投票で大政党のCDU/CSU、SPDに投票した有権者の95%までは、小選挙区でも同じ政党の候補者に投票する。ところが、政党名簿投票でFDPや緑の党に投票した有権者の40〜50%は、小選挙区で大政党の候補者に投票するという統計結果が出ている。
超過議席を認める制度ゆえの投票行動なのかどうかは分からないが、ドイツ型の小選挙区比例代表併用制でも、小選挙区では大政党に有利になっている。
太田光征
http://otasa.net/
トラックバック URI : http://kaze.fm/wordpress/wp-trackback.php?p=220