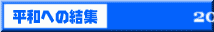ガダルカナルから見えてくるもの(彦坂 諦、小金原・憲法九条の会、2013年11月30日)
千葉県松戸市の小金原・憲法九条の会が2013年11月30日、講演会「”戦争”を語る」を開催しました。話者は『ある無能兵士の軌跡』シリーズの彦坂 諦さん。
演題は「ガダルカナルから見えてくるもの」となっていますが、福島原発事故と特定秘密保護法案を抱える今こそ、考えるべき内容です。
「嫌になるほど、あきれるほど、ちっとも変わってませんから、この国は」
乗り越えるべきは、福島原発事故と特定秘密保護法案そのものだけではないことが、分かります。
以下は、話者ご本人から提供いただいた講演の「台本」です。
太田光征
*
ガダルカナルから見えてくるもの
2013年11月30日
小金原・憲法九条の会
話者 彦坂 諦
はじめに
ガダルカナルから見えてくるものについて話してほしいという依頼を受けました。このいまじつに適切な発想だとおもいます。というのも、いまから68年まえに「大日本帝国」という名の国家の敗北によっておわった戦争のなかでも、このガダルカナル戦では、この国家の軍隊ののあらゆる病巣が露呈されているからです。
ガダルカナル戦の経緯を追っていけば、そこから見えてくる欠陥は、いくつもあります。なぜ見えてくるのか? そういった欠陥が21世紀のいまのこの国のあらゆるところにそっくりそのままと言ってもいいようなかたちで残っているからです。
これから具体的に指摘していくその病巣のどこがどのようにいまだに残されているのかといったことには、わたしは、ほとんど触れないつもりです。ですが、どうか、福島第一原子力発電所の大事故とその処理のしかたや「特定秘密法案」を制定しようと躍起になっているひとたちのふるまいなどをおもいうかべながらおききになってください。
A.なにがおこったのか?
ガダルカナル戦でおこったことは、2点に収斂します。
1.日米開戦以来はじめての惨憺たる敗北であったことです。この敗北のしかたが、そして、その後のどの戦闘でもくりかえされていくのです。
2.大量の飢え死をだしたことです。
ガダルカナル島に送りこまれた日本軍将兵の数は30000人あまり、
死んだひとは、約20000人です。この20000人のうち、
戦闘で死んだのは5000〜6000人、
のこりのほぼ15000人(75パーセント)は飢え死です。
A.1. 惨憺たる敗北
要するに、失敗につぐ失敗の連続でした。
まず、せっかくつくりあげたばかりの飛行場を米軍にやすやすとうばわれてしまった。 これを奪還しようと送りこんだ一木支隊は目的地にたどりつくまえに壊滅させられた。 つぎに送った川口旅団も、目的を達成する以前に密林にのまれて消滅した。
こんどこそというので送りこんだ第二師団による「大攻勢」も、計画は壮大だったが、そのなかばも実現しえぬまま、これまた密林にのみこまれてしまった。
あとは、食糧の供給も絶たれた敗残兵が密林のなかでいたずらに飢え死にしていくままにまかせた。
A.2. 飢えて死んでいく兵たち
わたしが説明するよりも、じっさいにその現場にいたひとたちの証言をいくつか紹介しましょう。それぞれ資料としておわたしてあります。では、その1から。
資料1 死なないうちに蠅がたかる
死なないうちに蠅がたかる。追っても追ってもよってくる。とうとう追いきれなくなる。と、蠅は群をなして、露出されている皮膚にたかる。顔面は一本の皺も見えないまでに、蠅が真っ黒にたかり、皮膚を噛み、肉をむさぼる。
そのわきを通ると、一時にぶーんと飛び立つ。飛び立ったあとの食いあらされた顔の醜さ、恐ろしさ。鼻もなく、口もなく、眼もない。白くむき出された骨と、ところどころに紫にくっついている肉塊。それらに固りついて黒くなった血痕。(中略)思わず面をそむけると、何百という蠅の群れは、再び地べたの腐肉にむさぼりついた。
(歩兵第124聯隊、聯隊旗手、小尾靖夫少尉の日記)
資料2 墓標のない墓場、埋められていない埋葬地
まだ蠅のたかっているもの、白骨になっているもの、睾丸を大きくふくらましているもの、手足の骨がバラバラになって道に散り、人の踏むにまかせているもの、こちらのボサに、あちらの草むらに、無気味な肉塊は後をたたぬ。墓標のない墓場、埋められていない埋葬地、その墓を縫って道が続いている。歩くたびに、足もとから蠅が舞い立ち、また腐った頬に、額に、唇に帰ってゆく。木の間を洩れてくる月光に浮ぶ髑髏は、黒々と眼窩をあけて怨むが如く足もとに転がっている。木の枝かと思ってうっかり踏むと、白い骨がポキリと音をたてたりした。
(第二師団コカンボナ糧秣交付所勤務吉田嘉七曹長の手記)
資料3 「コカンボナ糧秣交付所にありて」
椰子折れて倒れし道を
前線よりよろめき来たる
数人の兵をつれたる
将校の、われに頭を下げ、
給わらば我食うならず。
一線は補給とだえて既にひと月
密林は焼き払われて
わずかに残りし青き葉はなべて喰えど、
未だ来ず、米だに、塩だに、
戦友は待ちに待てれば、
かくわれら出で来しものを、
一粒にても、一かけにても得たきものをと、
ひたすらに乞える言葉や。
鋭くもわが胸をつき、煮え沸る腸の
いかにとや我は答えん。
連絡は早くとだえて、
交付所とは既に名のみに、
糧秣はかげすらも無く、
今椰子の実にいのち依る身の
苦しさや、はりさけんわが心。
ああ、いかにとや我は答えん。
好みてはなど断らん。
補給はこれわが任なるを。
かかる間も憎さも憎し、
これ見よがしに敵機来てまう。
(資料2の筆者とおなじ)
資料4 非科学的であり非人道的である生命判断はけっしてはずれなかった
どうやらおれたちは人間の肉体の限界まで来たらしい。生き残った者は全員顔が土色で頭の毛は赤子のウブ毛のように薄くぼやぼやになってきた。黒髪がウブ毛にいつ変ったのだろう。体内にはもうウブ毛しか生える力が、養分がなくなったらしい。(中略)やせる型の人間は骨までやせ、肥る型の人間はブヨブヨにふくらむだけ。歯でさえも金冠や充填物が外れてしまったのを見ると、ボロボロに腐ってきたらしい。歯も生きていることをはじめて知った。
このころ、アウステン山に不思議な生命判断が流行りだした。限界に近づいた肉体の生命の日数を統計の結果から、つぎのようわけたのである。この非科学的であり非人道的である生命判断はけっして外れなかった。
立つことのできる人間は……寿命は30日間
身体を起して坐れる人間は……………3週間
寝たきり起きれない人間は……………1週間
寝たまま小便をするものは……………3日間
ものを言わなくなったものは…………2日間
またたきしなくなったものは……………明日
(資料1とおなじ小尾少尉の日記)
よく、なんにも食べるものがなかったので、ヘビやトカゲまで食べたといった話をききますが、そんなのはまだ飢えていないときのはなしです。ガダルカナルの密林のなかで餓死しかけた赤松元一等兵の語るところによると、ほんとうに飢えて死ぬ寸前にいたると、ヘビやトカゲのようにすばしこいものなど論外で、すこしでも動くものなどとうていつかまえる体力はのこっていない。木の根、草の根を食べて飢えをしのいだというはなしも、すくなくともガダルカナル島の密林のなかではありえない。密林のなかには、生命力の旺盛な植物がおいしげっています。しかし、食べることのできない。豊穣のなかの飢餓です。
椰子の実ははじめのころは食べることができた。しかし、すぐに米軍の猛烈な砲爆撃で椰子はねこそぎたおれてしまっていたそうです。
あることをおもいだしました。『餓死の研究』(立風書房、1992)を書く準備をしていたころ、わたしは、第二師団の軍医としてガダルカナルにいたお医者さん3人にいろいろなことを語ってもらいました。そのうちのおひとりは、飢えた兵を診療するどころか御自身が餓死しそうになった体験をおもちでした。わたしは、医師の立場から、あの事態をどう見るのかをききたかったので、医学書に記載されている症状を並べ、それに対する御意見を具体的にうかがおうとしたのですね。このわたしの長広舌をじっと聞いていたこのかたが、さいごになんと言ったか。「そんなもんじゃないんだね。そんなに細かい医学的なものじゃないんだ。(中略)そこに書いてあるような、全身衰弱とか栄養不良とか、そんなカンタンなもんじゃないんですよ、そんな! グロッキーなんですから、もう!」
もうひとつ、ガダルカナル戦での餓死に関してこれまで発表されてきたほとんどすべての文献から無視されている問題点を指摘しておきます。餓死への道にも階層秩序(ヒエラルキー)があった、という事実です。現地軍の軍司令官は餓死していません。幕僚たちもです。他方、食糧の補給が途絶するまではとにもかくにも「給与」を受けていた兵たちでも飢えて死んでいった状況のなかで、しょっぱなから、食糧の配給をまったく受けられなかったひとたちが現にいるのです。
わたしがこれまでつかんでいるかぎり、つぎの4種類のひとたちがいます。
1.飛行場建設に従事していた徴用工たち
2.おなじ作業に従事していた朝鮮人土工たち
3.沈められた船から泳いで上陸した船員たち
4.おなじく泳いで上陸した船舶高射砲兵たち
わたしのシリーズ「ある無能兵士の軌跡」(全9巻)の主人公赤松元一等兵はこの「4」に該当します。彼が船舶高射砲兵として配属され、乗船勤務していた九州丸は、いまでもガダルカナル島タサファロングの沖あいに残骸をさらしています。もうほとんど海中に没してはいるのですが。船が沈められた位置が海岸線からそれほど遠くなかったので、赤松さんは、燃えさかる船から自力で脱出し、泳いで岸にたどりつきました。以来、餓死寸前の状態で救出されるまでの4ヶ月間、ただの一度も、軍から食糧配給を受けたことはなかった、と証言しました。
理由はただたひとつ、彼らの小隊は所属する聯隊から離れた独立小隊として九州丸に乗り組んでいたため、泳いで上陸してみても、所属部隊がなかった、つまり軍隊用語では「員数外」とされる存在だった、ということです。
おことわりしておきますが、のちにフィリピン戦などで頻発する「遊兵」つまり、所属する隊から棄てられたり脱走したり、あるいは隊そのものが壊滅したり組織崩壊したりしたために、隊から離れてひとり山中をさまよう兵たちと、赤松さんたちとはちがうってことです。赤松さんたちはまがりなりにも小隊としての組織は維持していた。小隊長も、グヮラーンとなってしまってはいたけどまだ死んではいなかった。それでも軍からの「給与」は受けられなかった。員数外だったから。
正式の兵隊にしてこのようなありさまです。だったら、兵員ではない徴用工や強制連行されてつれてこられた土工たち、あるいは沈没して用ずみになった船員たちにおいておや。この差別に気づいている文献に出会ったことは、残念ながらありません。
B.なぜ、こんな事態になってしまったのか?
これもふたつの要因にしぼられます。むろん、截然とわけられるものではなく、密接にからみあっているのですが。
1.日本軍の首脳部つまり大本営の参謀諸氏が立てた作戦計画そのものが非現実的なものであったこと。
2.計画立案にさいしてカンジンカナメのことについて無知であり、したがってそれを無視したこと。
B.1 ひとりよがりの計画立案(敵を知らず己を知らざれば百戦ことごとく危うし)
ひとくちで言うと、とうぜん想定できたはずのことがらを無視し、いざことがおこってしまうと、これは想定外であったと弁明する、そういった風習が、大日本帝国軍隊のとりわけ中核の部分にはあったからです。
現実をきちんと見すえないままで、つまり客観的分析を無視して、というよりはじめからやろうとしないままで、ただ、そうあってほしいという願望だけにもとづいて計画が立案されていた。
だいいちアメリカを敵とする戦争の計画そのものが主観的なものにすぎなかった。それが天皇の命令として確定されていくおかしさ、わらうにもわらえない独特の会議運営について、わたしは、かつて、「だれもが反対なのに戦争になってしまった」という皮肉に充ちた文章を書いています。
ガダルカナル島で日米両軍が死闘を演ずることになった。そもそもの原因は、日本海軍がこの島に飛行場をつくったことにあります。なぜ、こんなところにつくったのか?
太平洋地域の地図をおもいうかべてください。アメリカの西海岸とオーストラリアの東海岸の主な港湾都市、たとえば、サンフランシスコとシドニーとを直線で結んでみてください。その線は、サモア、フィジー、ニューカレドニアといったあたりを通るでしょう。で、これらの島々を占領してそこに軍事基地をつくってしまえば、太平洋における敵の二大勢力アメリカとオーストラリアとの連絡を遮断できると、日本側は考えた。この計画は、フィジーとサモアとの頭文字をとってFS作戦と名づけられました。
ガダルカナル島は、この作戦を遂行するうえでの恰好な前進基地となりうる。だから、ここに航空基地をつくった。ところで、こちらがわにとって都合のいいことは、とうぜん、あちらがわにとっては都合のわるいことです。ですから、これまた当然のことながら、この計画を阻止しようとする。そう予測するのが常識です。
ところが当時の日本軍首脳はそうは思わなかったらしい。なぜか? 相手をみくびっていたのですね。アメリカと戦争をはじめたばかりのころは、それこそ連戦連勝だったから。
とはいえ、いくらひとりよがりの日本軍首脳にしても、相手がこのままおとなしくひきさがるだろうとまでは考えられなかった。いずれ反撃はされるだろう。しかし、その時期は早くても1943(昭和18)年以降であろうと想定していた。なにしろあれだけ徹底的にたたきのめしておいたのだから、連中もそう簡単には立ちなおれまい。
そう信じこんでいた日本軍首脳は、開戦当時にはおもいもよらなかったかった広大な地域にまで戦線をひろげてしまった。
北はアリューシャン列島、
東はミッドウェー、
南はソロモン、フィジー、サモア、ニューカレドニアまで、そして
西はビルマまで。
この勢いにのって、ガダルカナル島の飛行場建設ははじめられた。完成したのが1942(昭和17)年の8月です。ところが、このときすでに米軍の猛烈な反撃がはじまってしまった。ガダルカナル島の飛行場は、やすやすと米軍に奪われてしまいました。まさに想定外の事故がおこった。
やすやすと奪われてしまったのは、こちらがわがほとんど無抵抗だったからです。抵抗のしようもなかった。奪いに来た米軍のほうは、
輸送船23隻に約2万名の海兵隊を乗せ、
巡洋艦と駆逐艦と空母も含む護衛艦隊総勢82隻、
上空から上陸を支援する航空機293機といった、
どう見ても本格的な正面攻撃の態勢であったのに対して、
そのときガダルカナルにいた日本軍はというと、
飛行場設営隊およそ2600人、
警備隊がおよそ250人、あわせてもおよそ2850人だけ、
しかもその設営隊員の85%つまりほぼ2200人は、徴用してつれてきた非戦闘員の工員と、朝鮮半島からおそらくは強制連行してきた土工でした。どう見ても、これは手薄どころのはなしじゃない。防備兵力はゼロにひとしかった。
なぜ、そんなことになっていたのか? 護る必要などないとおもっていたからです。あのような事態は想定外であったからです。日本軍首脳は、ここの時点で敵が攻めてくる気づかいはないと踏んでいた。よしんば攻めてきたとしてもせいぜい威力偵察程度の小兵力であろうという先入観に支配されていた。
もういちど言いますが、あれほどたたいたのだから容易に立ちなおることはできまいといった考えは、蟹は甲羅に似せて穴を掘るのたぐいです。自分たちの国では、致命傷を負ったり沈んでしまったりした軍艦を修理したり新しくつくったりすることなど簡単にできはしない。だからアメリカもそうだろうと考えた。アメリカという国家の経済力をはなから嘗めてかかっていたから現実が見えっこない。
じっさいにはどうだったのか? 日本側が撃沈したといって凱歌をあげていた艦艇はたちまち新しく建造されていた。修復不可能なダメージをあたえた(軍事用語では大破したと言います)ばあいも、さっさと修理して戦線に復帰させていた。
大本営参謀諸氏には近代の戦争がどういうものかがまったくわかっていなかったのですね。戦後になってからわかったことですが、たとえば、戦争をつづけるには必要不可欠な鉄鋼の生産量は、日本では日米開戦のときがピーク。あとは下がる一方でした。逆にアメリカでは右肩あがりに増えています。国力の差は歴然です。
もっとずっと以前から戦争は総力戦になっています。いくら緒戦の戦闘で景気よく勝ったとしても、国力がつづかなければ、わけても経済力がおちこんでしまえば、軍事力もテキメンにおちこむ。
ガダルカナルの飛行場が占領されてしまったときですら、これがアメリカ軍による本格的反攻のはじまりなんだと認識することができなかった。こういった先入権に支配されていたからです。
この最初の致命的誤認がつまづきのはじまりでした。あとは一時が万事、打つ手打つ手がみな後手であり、しかも致命的誤算ばかりでした。
B2 補給に関する無知・無関心.
身体が消費したエネルギーを食べることによっておぎなえなければ人間は死んでしま
う。その、生きるために必要な食糧を、日本軍首脳は将兵にあたえることができなかった。
ガダルカナルにかぎらず、海外のあちこちに「投入」した兵たちに対する後方支援という考え、いや意識が、日本軍首脳には、具体的には大本営の参謀諸氏には根本的に欠けていたようです。
日本軍の首脳がいくらぼんくらぞろいで兵たちのいのちを軽んじていたとしても、食糧の供給を意図的にさぼっていたわけではありません。なんとか送ろうとはした。ただ、それがこの島まで届かなかった。食糧を積んだ船が途中で沈んでしまったからです。
船は自然に沈んでいくものではありません。攻撃され、沈められるのです。だとしたら、ちゃんとした護衛をつけておけばいい。けど、その力がもう日本軍にはなくなっていました。
ありていにいうと、この当時ソロモン海域では、制海権も制空権ももはや米軍の手ににぎられていた。つまり、米軍の輸送船なら白昼堂々とガダルカナルのどの海岸にも大量の兵員や武器弾薬や食糧や医薬品やトラックや建設資材や、映写機やフィルムやレコードプレイヤーまでも運びこむことができたのに、日本軍の兵隊や武器弾薬に食糧を積んだ船は途中でしずめられずに無事目的地に行きつける保障などもうなくなっていたのです。
それに、もっと根本的な原因があった。もともと、日本軍首脳には、具体的には大本営の参謀諸氏には、軍事行動をおこすには補給線の確保が必要不可欠であるということがわかっていなかった。わかっていたら、補給線の確保が困難だと予想される地域にまで戦線を拡大するはずはない。
C.困難な事態にどう対処したか?
C.1. 事態を軽くみようとする(過小評価)
ガダルカナルの飛行場が米軍にあっさりと奪われてしまった時点で、現実には大兵力による本格的正面攻撃であったのに、せいぜい2000名程度の威力偵察であると誤認した。だから、これに対抗するには、北海道旭川の歩兵第28聯隊の一部(一木支隊)900名ほどを「投入」すればことたりると判断した。
戦車も大砲も充分にそなえ弾薬も食糧もたっぷり用意している2万名のアメリカ海兵師団に対抗するのに、いくら精兵ぞろいだといっても900名ほどの兵に弾薬も食糧もろくすっぽあたえないまま、なぐりこみをかけさせるなど、狂気の沙汰であるのに、軍首脳にはそのことがまったくわかっていなかった。
一木支隊の戦闘はまさに砲兵と歩兵とのたたかいでした。米軍の猛烈な砲撃によって、一木支隊は、その精鋭ぶりを発揮する機会そのものを封殺されて、むなしくついえてしまった。つまり白兵突撃をなしうる地点まで接近する以前にみなごろしにされてしまった。わずかに生き残った敗残兵たちの前に用意されていたのは、飢えて密林のなかをさまよいあるき、死んでいく運命でした。
この戦闘でガダルカナル島イル川(日本軍の呼称では中川)の砂州に残された一木支隊将兵の累々たる屍と、幽霊のように密林をさまよう飢えた兵たちのすがたとは、その後いくたびも、この島で、いや、この島以外の多くの島々で、性懲りもなくくりかえされていく戦闘パターンの象徴とも言えるものでした。
一木支隊の失敗の原因を大本営の参謀諸氏は深刻に感じとる力がなかった。単純に、やはり人数がすくなすぎたのかと考えて、こんどは旅団規模の川口支隊を派遣することにした。旅団規模というのは戦時編制では8000人ほどです。
この8000人のうち、じっさいにガダルカナル島に到着して川口旅団長(中将)の指揮下に入りえたのは6000人(5個大隊)程度にすぎなかった。なぜか?
行こうとしても行けなかったのです。8000人もの兵員をそれ相応の装備とともに遠い島まで運ぶには輸送船を使うしかない。しかし、輸送船団に護衛艦隊を配備することなどできなくなっていた。だから、川口支隊も、一木支隊とおなじように、駆逐艦や上陸用舟艇程度のボートに分乗して、渡った。そんな無理をしなければならなかったのも、すでに指摘したように制海空権を米軍にうばわれてしまっていたからです。6000名もの兵が無事上陸できただけでも、のちにくらべれば奇跡的な成功です。しかし、兵たちは上陸したが武器弾薬はほとんど届いていない。
この時点でもまだ、大本営参謀諸氏は、米軍はたかだか5000名に戦車が30台、15?砲が数門くらいだろうと踏んでいた。この程度であっても、しかし、戦車どころか大砲もろくすっぽ持っていない川口支隊が正面から攻撃しかけたのでは勝ち目がうすかろう。そう判断したから、日本陸軍のお家芸である夜襲をかけることにした。つまり密林に潜入迂回して敵の背後を衝こうと考えた。これが深刻な事態をまねく。
ガダルカナル島の密林のなかに潜入迂回して敵陣の背後を衝く。地図だけ見て作戦を立てる連中には卓抜な作戦であったのかもしらないが、いや、現地を知らないにもほどがある。ガダルカナルの密林がどういうものなのかを、参謀諸氏のひとりとして知る者はいなかった。
ガダルカナル島の密林というのは、千古不抜、人跡未踏のおそろしいところです。大木が空を蔽っているから陽の光が地面にとどかない。だからいたるところぬかるみだらけ。そのぬかるみに足をとられながらあえぎあえぎ進む兵の前に巨木な倒木が立ちはだかる。乗りこえることなどできやしないから、避けて進む。そんなことをやってるうちに方角を見失う。難渋して計画どおりの速度では進めない。体力も消耗するし、乏しい食糧もつきてしまう。川の水は日米両軍の糞便で汚染されているから、飲んだら下痢をする。大木がいたるところで道をふさぐ。踏みこんだら最後、密林にのみこまれてしまうのです。
一木支隊の攻撃のときより一段と強化された防衛陣を構築し手ぐすねひいて待ちかまえていた米軍に、密林のなかで消耗しきった日本兵がとにもかくにも突入していったのですから、勝負になるはずがない。生きのこった兵たちを待っていた運命は一木支隊のばあいとおなじ。密林のなかをさまよいあるき餓死していく。
こんどこそ、大本営の参謀諸氏もここからの教訓をくみとったか? だれひとり、なにひとつくみとりはしなかった。それでも、兵力の「逐次投入」はいけないってことだけはわかったらしい。兵力の逐次投入とは、必要なときに必要な兵力を一挙に投入することをためらって、ケチケチと小出しにしていくことです。
こんどこそ大兵力を動員して正攻法でいこうというので、大本営は、第二師団を主力とする総員28000名の本格的増援軍を、火砲200門、戦車と軽装甲車75両とともに送りこみ、この軍団の上陸予定日までには、1ヶ月分の食糧と8000トンの弾薬を輸送集積しておくといった壮大な計画をたてました。
しかし、ここでもまたおなじこと。机のうえで計画を立て、命令をくだしさえすればそれが遂行されるものとはかぎらない。最大のネックはまたしても輸送でした。これだけの大兵力をはこぶとなればもう輸送船をつかうしかない。1万トンクラスの大型高速船ばかりの6隻で船団を組み、当時としてはこれ以上のぞめない強力な支援艦隊を海軍につけてもらって、一挙にソロモン海をおしわたるはずだった。
結果的にはこれも大失敗におわる。たしかに、護衛艦隊は6隻の大型船を無事ガダルカナルまで送りとどけることができた。船員も船舶砲兵も船舶工兵も、米軍の猛烈で執拗な銃爆撃のもとで文字どおり生命を賭して揚陸作業をおこないました。
にもかかわらず、輸送船6隻のうち3隻はせっかくたどりついたガダルカナル島タサファロング泊地で沈められてしまった。積荷のうち揚陸できたのは半分にみたず、その大半が、せっかく海岸までは揚げたものの密林のなかまで運ぶ手順がうまくいかずに放置されているあいだに、猛烈な砲爆撃によって焼きつくされてしまった。兵たちだけは泳いで上陸できたが、丸腰で人間だけ島にあがったところでこの先戦えるわけがない。結局、当初の計画の半分も達成できなかった。
となると、当然のことながら「大攻勢」などできるはずがない。だから、またしても「密林潜入迂回・夜襲」作戦となった。川口支隊の失敗の二の舞です。
C.2 過去から学ぼうとしない。
わかりやすい例だけをあげましょう。ガダルカナル戦のわずか3年まえにノモンハン戦争がありました。日本側ではこれまた戦争という表現をさけて「ノモンハン事件」と称していますが、モンゴル共和国側の正式名称は「ハルハ河戦争」です。旧満州国とモンゴルとの国境付近で日ソ両軍が戦闘をおこなった局地戦です。
この戦闘で日本軍は完膚なきまでたたきのめされた。すでに機械化されていたソ連軍とむかしながらの日本軍との力量のちがいが歴然とした戦闘でした。日本軍には三八式歩兵銃と手榴弾しかなく、お家芸の白兵戦にもちこむ以前に ソ連軍の戦車と航空機と機関銃との攻撃にやられて壊滅してしまった。
この苦い経験が、ガダルカナル戦ではいっこうに生かされることなく、強力に機械化されたアメリカの大軍に、またしても少数精鋭で白兵戦をいどもうとした。だから、突撃にまえへ! という命令をくだしうる地点まで肉薄などできるわけがなく、そのはるか手前で壊滅しています。歩兵が三八式銃だけで砲兵にいどめば勝敗はあきらかです。
一時が万事。あの戦争のどの過程においても、どの戦場にあっても、過去の経験に学ぶこと、具体的には過去にやらかした失敗から教訓を得ようとすることはせずに、ただがむしゃらに、これまでとおんなじことをくりかえしたと言っていい。
C,3..官僚主義
日本にかぎらずどの国家にあっても軍という存在はそれ自体が膨大な官僚組織ですから、そこでおこなわれている行動のすみずみまで官僚主義が浸透している。これは常識です。それにしてもとりわけ「大日本帝国軍隊」にあっては官僚主義の弊害が他に類を見ないほど大きかった。
官僚主義にあってもっとも特徴的なことは、上部の専決と下部の盲従です。むろん、上部がかってになにもかも決めるといったことは、じっさいには、ありえません。上部は、下部からの報告にもとづいて、目標を定め、計画を立て、命令として下達するのです。
問題は、この下部からの報告つまり上部への情報伝達のありようなんですね。要するに、下部は上部のお気に召すような情報しか伝えない。正直にありのままを伝えようものなら、どんな眼にあうかわかっていた。きさま、やる気あるのかと、どなられ、ののしられ、なぐられ、足蹴にされる。
いいことづくめの報告にもとづいて上部が策定する作戦計画なのですから、現場の実情からかけはなれた、達成しようにもその現実的基盤のない命令となって現場の将兵を苦しめることになるのです。
ガダルカナル戦における例をひとつだけあげておきます。第二師団による「10月大攻勢」を「密林迂回」によって実施することに決定したのは、第17軍高級参謀の小沼大佐が密林の状況を「視察」した結果、密林迂回は可能であると判断したからだ、と防衛庁の公刊戦史には記載されています。けど、この「視察」とはじっさいに密林のなかに足を運んで状況を観察したのではなく、軍司令部付近の「展望台」から双眼鏡でのぞき、密林にはすきまも見うけられると「判断」したにすぎなかったのです。
この判断にもとづいて密林のなかを進軍するように命令された兵たちが、さて、じっさいに足を踏みいれてみると、実情はどうだったのか? このことについては、すでに川口支隊のところでのべたとおりです。
おわりに
ガダルカナル戦から見えてくる病巣はこのほかまだいくらでもあります。ひとつひとつ指摘していけばきりがない。アトランダムにあげてみれば、つぎのようなこと。
1.大言壮語
声の大きいひとの意見にひきずられて大勢がきまってしまう。あるいは、根拠薄弱なところを大言壮語で糊塗すると。
2.住民無視
作戦計画遂行の邪魔になるばあいには、そこに先祖代々くらしているひとたちのくらしなど平然と蹂躙する。
3.気魄の誇示
たんなるジェスチャーでもいい、やる気のあることを誇示すればすむ。なんの根拠もなく、だれもほんとうはその意味などわからないスローガンをがなりたてる。
この姿勢は「精神主義」と一般には言われているようですが、それでは精神に対して失礼であろうとわたしは考えます。精神=spiritというのは、たとえようもなく高潔なものです。それを汚すような言いかたですよ、これは。いたずらに大和魂をふりまわすようなふるまいは、たんなる神がかりにすぎません。本来の精神主義とはまったくカンケイナイ。
4.情報の完全な統制と秘匿
すべての情報が完璧に統制され秘匿されていた。日本本土から6000キロも離れた南太平洋上の島で日本軍とアメリカ軍が戦争をしていることだけは、国民にも知らされていた。けど、その実態はまったく知らされていなかった。
日本軍が勝ったという報道だけは、じっさいよりはるかに誇大であり、またウソっぱちであったことがのちにばれたとはいえ、戦意昂揚に役立つものとして流された。だから、まさかあの島で兵隊さんたちが飢えて死んでいっているなんてことは、わたしたちはまったく知らなかった。
戦時中の情報統制は完璧でした。ラジオで流される天気予報ですら、いまならさしずめ特定秘密指定と言うんでしょうねえ、軍事機密あつかいでした。
ほかにもまだまだあります。考えることをやめる、つまり思考の停止、「かたづける」という思考。なんでもいい、その場から見えなくしてしまうのがかたづけるってこと。しまいには自分もかたづけてしまう。
しかし、さいごにはっきりと言っておきたいのは、ガダルカナルから見えるものすべてをつらぬいているのはなにかってことです。
いのちをたいせつにしない、いや、かろんずる、という思想です。
もともと「大日本帝国軍隊」にあっては、兵のいのちなどけっして尊重されなかった。人命軽視はまさに軍人の本分でした。
軍人勅諭の第一項「軍人は忠節をつくすを本分とすべし」のなかに「義は山嶽よりも重く死は鴻毛よりも軽しと覚悟せよ。その操を破りて不覚を取り汚名を受くるなかれ」といういましめがありました。このいましめが「戦陣訓」のいましめと重なりあって日本軍将兵に捕虜となるより死を選ぶという行動をとらせたことはつとに有名なところです。
もともとどこの国のどのような軍隊であれ、それが軍隊であるかぎり、兵は、どうにでも自由につかうことのできる道具=物にすぎません。とはいえ、兵の生命をどれほど尊重するかどうかは、軍隊の質やその背景にある社会の文化によってことなります。もっとも、倫理的宗教的な背景があって人命が尊重されるのか、それとも、「戦力」としての軍人の効率的養成と利用という観点からなのかは、そうそう厳密に分けられるものではありませんが。
ともあれ、兵は死んでもかわりはいくらでもある、というのが軍の思想です。よく言われたように兵のいのちは軍馬のいのちよりもおとっていたのです。軍隊用語では兵たちが死んで戦力が低下するのを補うために新たに兵をおくりこむことを補充と言います。物品の補充となんらかわらない概念です。
トラックバック URI : http://kaze.fm/wordpress/wp-trackback.php?p=514