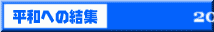日弁連会長が「裁判員制度、予定通り開始を」と呼びかける緊急声明を発表するとはどういうことだ!!
昨日(8月20日)付朝日新聞が「『裁判員制度、予定通り開始を』 日弁連が緊急声明」という記事を掲載しています。
http://www.asahi.com/national/update/0820/TKY200808200282.html
日弁連会長が「裁判員制度、予定通り開始を」という緊急声明を発表??
少なくない各県単位弁護士会から来年度実施予定の「裁判員制度」への疑問が提出され、多くの弁護士の間からも同「裁判員制度」への疑問が噴出しているときに、これはどういうことでしょう?
私が知っている限りにおいても、以下の単位弁護士会から来年度「裁判員制度」実施への疑問が提出されています。
■裁判員制度の抜本的見直しと実施の延期を求める総会決議(栃木県弁護士会 2008年5月24日)
http://www.tochiben.com/topics/news26.html
■裁判員裁判実施までに解決すべき課題に関する決議(平成20年5月21日 大分県弁護士会総会決議)
http://cgi37.plala.or.jp/~oitakenb/syosai.cgi?2=121141690017191
■取調の全過程の録音・録画を求める決議(平成20年2月23日 大分県弁護士会総会決議)
http://cgi37.plala.or.jp/~oitakenb/syosai.cgi?2=120408814823165
注:同弁護士会は、「来年実施される裁判員裁判で、取調の(全面)可視化(録画化)が採用されない限り、スタッフ弁護士、大分県の弁護士会全部ボイコットする」とまで言っています(関東弁護士会連合会会報)。同弁護士会の上記ボイコットの決意は、私も、同弁護士会の裁判員制度問題の責任者を含む複数の弁護士から直接ナマの声で聞いて確認しています。
■裁判員裁判実施の延期に関する決議(新潟弁護士会 平成20年2月29日)
http://www.niigata-bengo.or.jp/info/resolution/resolution.shtml?416
※決議理由:http://www.niigata-bengo.or.jp/info/resolution/reason.shtml?416
■取調べ全過程の録音・録画の実現を求める総会決議(新潟弁護士会 平成20年2月29日)
http://www.niigata-bengo.or.jp/info/resolution/resolution.shtml?415
※決議理由:http://www.niigata-bengo.or.jp/info/resolution/reason.shtml?415
その他、「裁判員制度」への直接の言及はありませんが、同制度の実施と密接にリンクしている取調べの可視化の問題について、日弁連、自由法曹団が総会決議、また意見書として、現在の状況についての強い危惧の念を表明しています。
■取調可視化法案の今国会における成立を求め,調べ可視化に抵抗する警察庁の姿勢を批判する意見書(自由法曹団 2008年4月22日)
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/080422kashika.pdf
■第58回定期総会・取調べの可視化(録画・録音)を求める決議(日弁連総会決議 2007年5月25日)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/ga_res/2007_1.html
上記の日弁連会長の緊急声明は、これらの弁護士、弁護士会の多数の意志を無視し、そしてなによりも自らがその組織の長として拠って立つ日弁連総会決議さえほごにする独断、独走、横暴というほかないのではないでしょうか?
この日弁連会長の独断、独走を全国の弁護士たちはこのまま許してしまってよいのでしょうか?
日弁連会長に対して、その独断、独走をただちに抗議するべきではないでしょうか?
以下、上記のことを伝える報道と日弁連会長声明です。見られるとおり、日弁連会長声明は、各弁護士会からの来年度実施予定の「裁判員制度」に対する重要な疑問、問題提起を意図的に無視し、裁判所、検察の広報係りに成り下がっている感があります。
民主主義のためにも、真に市民のための裁判制度の確立のためにも許されることではない、と思います。
……………………………………………
■「裁判員制度、予定通り開始を」 日弁連が緊急声明(朝日新聞 2008年8月20日)
http://www.asahi.com/national/update/0820/TKY200808200282.html
来年5月に始まる裁判員制度を前に、野党から「国民の理解が不十分だ」として施行の延期を求める意見が相次いだことを受けて、日本弁護士連合会の宮崎誠会長は20日、「新制度で戸惑いがあるのは事実だが、延期すれば、欠陥を抱えた現行の刑事裁判が続くだけだ」として予定通りの開始を求める緊急声明を発表した。
声明は、「捜査も裁判も官のみが行う状況ではチェックが働かず、冤罪はなくならない」と指摘。「これを変えるためには、市民に裁判に関与してもらうことが不可欠」と国民に理解を求めている。
裁判員法は04年に全会一致で成立したが、今月に入って共産、社民の両党が制度の延期を求める見解を発表。民主も幹部が見直しの必要性に言及している。
……………………………………………
……………………………………………
■裁判員制度施行時期に関する緊急声明(日弁連会長声明)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/080820.html
最近、一部から、来年5月21日から施行される裁判員制度の施行時期を延期すべきではないかという意見が表明されています。
しかし、当連合会は、刑事弁護を担ってきた立場から、また、国民の司法参加を願ってきた立場から、裁判員制度が予定通り実施されるよう強く求めます。当連合会は、裁判員制度実施に向けて、今後とも万全の体制で準備にあたります。
人質司法と言われるように密室の中での違法不当な取り調べが横行し、自白しないと保釈が許されない、いったん虚偽の自白をすると、撤回が許されず、捜査官が作成した膨大な調書のみが積み重ねられます。そして、99.9%が有罪判決であるという状況の下で、裁判官は有罪判決を下すことに慣れてしまい、有罪判決を書くための要素のみを無意識にピックアップしてしまうおそれがあります。捜査も裁判も官のみが行う状況ではチェックが働かず、一向に冤罪はなくならないのです。
今回の法改正で、公判前整理手続が導入され、弁護人の活動により、捜査側の手持ち証拠が広範囲に開示されることになりました。再審開始決定された「布川事件」のような冤罪事件で問題になった捜査側の証拠隠しの防止のためには大きい改善であり、裁判の充実にも良い結果をもたらしています。
しかし、人質司法や調書裁判という刑事裁判の根本的な欠陥はそのままです。
これを変えるためには、市民のみなさまに裁判に関与していただき、無罪推定の大原則の下、「見て聞いて分かる」法廷で判断していただくことが不可欠です。
「見て聞いて分かる」法廷では膨大な調書は存在できませんし、捜査も自白よりも物的証拠や科学的な捜査を重視する方向に向かわざるを得ません。
市民のみなさまにはご負担をおかけしますが、是非とも裁判員裁判に参加していただき、みなさまの健全な社会常識を司法の場に生かしていただきたいのです。
事前のアンケートでは不安を覚える市民の方が多いという報道がなされています。
この点、同じ市民が司法に直接参加し、検察官の不起訴の判断の妥当性を判断する検察審査会では、守秘義務を負いつつも、多くの市民が日常生活を中断して参加されていますが、参加前のアンケートではやはり多くの市民の方が参加に消極的です。しかし、一度審査員を経験された後では、実に96%の市民の方が「参加して良かった」と言う御意見に変わっています。諸外国でもこのような傾向は同じです。裁判員制度は誰もやったことがなく情報も少ないためご不安を覚える方も多いと思いますが、問題のある刑事裁判を良くするために是非ともご参加をいただきたいと考えています。
もちろん、今の裁判員裁判制度に改善すべき点がないというわけではありません。また取調べの可視化(取調べの全課程の録画)なども極めて不十分です。しかし、裁判員制度を実施することによって、改善すべき点は改善し、また、取調べの可視化(取調べの全課程の録画)をさらに広げたり、調書裁判の弊害や人質司法の弊害を改善する動きを進めていくことが大切です。裁判員裁判を延期したのでは何よりも根本的な欠陥を抱えた現行の刑事裁判が続く結果となるだけです。
多くの冤罪弁護事件を支援し、刑事弁護を担ってきた当連合会は、裁判員制度を延期して今の刑事裁判を継続するのではなく、この制度を実施の上、欠点があれば、実施状況を見ながら改善していくという方法で進めるべきであると考えます。
世界に誇れる刑事裁判の実現に向けて予定通り実施されるよう、ここに改めて強く求めるものです。
2008年(平成20年)8月20日
日本弁護士連合会
会長 宮 誠
……………………………………………
東本高志
トラックバック URI : http://kaze.fm/wordpress/wp-trackback.php?p=225