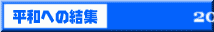大選挙区制(中選挙区制)の問題点 〜連記投票制の落とし穴〜
複数の候補者を選ぶ大選挙区制(中選挙区制)では、複数の議席を選ぶのだから、定数分の票を投じる連記投票制(有権者1人複数票)が、一見合理的なように思われます。実は日本でも、1946年の1回だけ、連記投票制を組み合わせた大選挙区制で選挙が行われました。ところが、連記投票制の大選挙区制(中選挙区制)は、小選挙区制と同様に大量の死票を生み出すことがあります。
では単記投票制(有権者1人1票)の大選挙区制(中選挙区制)はどうかというと、最も好まれた候補者を落選させるコンドルセのパラドックスを発生させます。
以下、大選挙区制(中選挙区制)の問題点を解説しておきます。(印刷用ファイル)
共同声明「国会議員の定数削減に抗議する」賛同募集中
【目次】
(1) 単記投票制の大選挙区制(中選挙区制)では最も好まれた候補者を落選させるコンドルセのパラドックスが発生する
(2) 連記投票制の大選挙区制(中選挙区制)は小選挙区制のように大量の死票を生み出す
(3) 連記投票制の大選挙区制(中選挙区制)は小政党に有利か
【関連投稿】
小選挙区制の廃止へ向けて
http://kaze.fm/wordpress/?p=215
中選挙区比例代表併用制を提案する
http://kaze.fm/wordpress/?p=164
小選挙区比例代表併用制の問題点
http://kaze.fm/wordpress/?p=220
比例区定数が100に削減された場合の衆院選比例区シミュレーション
http://kaze.fm/wordpress/?p=229
【参考文献】
西平重喜『比例代表制』(中公新書、1981年)
(1) 単記投票制の大選挙区制(中選挙区制)では最も好まれた候補者を落選させるコンドルセのパラドックスが発生する
具体例で考えてみましょう。定数が2で、A、B、Cの3候補が立候補し、投票者数は約30万人、A、B、Cの得票率はほとんど変わらないとします。つまり、それぞれ約10万票を得たとします。ただ、少しだけ得票数に開きがあり、単記投票制の場合の得票順位がA、B、Cだったとします。したがって単記投票制の場合の当選者はAとBの2人です。
投票の「中身」をもっと詳しく見ていきます。Aが一番好きだとする有権者の中では、BよりCが好きだという有権者が100%、Bが一番好きだとする有権者の中でも、AよりCが好きだという有権者が100%、Cが一番好きだとする有権者の中でも、AよりBが好きだという有権者が100%であったとします。
すると、もしも連記投票制で2票を投じることができる場合、第1希望と第2希望でAに投じる有権者は約10万人、第1希望と第2希望でBに投じる有権者は約20万人、第1希望と第2希望でCに投じる有権者は約30万人いると考えられます。したがって連記投票制なら、C、Bの順に当選し、単記投票制でトップ当選したAは落選します。
このように、大選挙区制(中選挙区制)の場合、単記投票制では民意を反映しない場合があります。小選挙区制で有名なコンドルセのパラドックスと同じ原理です。では、大選挙区制(中選挙区制)に連記投票制を採り入れればいいかというと、次のような問題点があります。
(2) 連記投票制の大選挙区制(中選挙区制)は小選挙区制のように大量の死票を生み出す
具体例で考えます。定数が10で有権者1人10票を投じ、与党Aから10候補が立ち、野党Bからも10候補が立ったとします。与党支持の有権者はすべて与党の10候補に投票し、野党支持の有権者もすべて野党の10候補に投票したとします。さて、野党支持の投票者数が、与党支持の投票者数より1だけ多いとします。すると連記投票制の場合、野党の10候補はすべて与党の10候補より1だけ得票数が多いことになります。結果は、10議席すべてを野党Bが独占します。
もしも上記のケースで比例代表制が採用されていれば、与党Aと野党Bはほぼ5議席ずつを分け合うことになるでしょう。
このように、大選挙区制(中選挙区制)に連記投票制を組み合わせると、著しく民意からかけ離れた選挙結果を生じることがあります。小選挙区制と同様、大量の死票を生み出します。
英国で過去に実例があります。「イギリスのノルウィッチ選挙区は、一九四五年まで二議席で、二名連記投票制だった。…このような二議席の選挙区がイギリスには一九四五年まで一一区あったが、この最後の選挙では、一一区とも全部一党によって独占され、一議席ずつ分けあったところはない」(西平重喜『比例代表制』、中公新書、p24、1981年)。
「フランスの小さな町村は、日本の大字ていどの規模のものが多いが、そこでの町村議会は、連記投票制に近い方式で、議会全体を一つのグループにゆだねようとしている」(同上書、p25)。
単記投票制であれば比例代表制に近くなる大選挙区制(中選挙区制)が、連記投票制を組み合わせることで、大量の死票を生み出す小選挙区制のような制度に変質する。かといって単記投票制の大選挙区制(中選挙区制)では、原理的に民意を反映しない。大選挙区制(中選挙区制)の本質的矛盾です。
(3) 連記投票制の大選挙区制(中選挙区制)は小政党に有利か
連記投票制であれば、1人の候補者に票を集中させることで、小政党の候補者でも当選させることができるのではないか、とも考えられます。簡単なシミュレーションを行ってみましょう。
定数が3で有権者1人3票制とし、大政党Aが候補者2人を立て、支持率50%、大政党Bも候補者2人を立て、支持率40%、小政党Cが候補者1人を立て、支持率10%とする。大政党Aを支持する有権者はすべて大政党Aの候補者2人に投票し、大政党Bを支持する有権者はすべて大政党Bの候補者2人に投票し、小政党Cを支持する有権者はすべて小政党Cの候補者1人に投票したとする。
上記のケースでは、大政党Aの候補者2人の平均得票率は75%(50% × 3 ÷ 2)、大政党Bの候補者2人の平均得票率は60%(40% × 3 ÷ 2)、小政党Cの候補者1人の得票率は30%(10% × 3)となる。したがって選挙結果は、大政党Aに2議席、大政党Bに1議席という公算が大きい。
もしも上記のケースで、大政党Aの支持率は50%のまま、大政党Bの支持率を30%、小政党Cの支持率を20%に変えれば、大政党Bは議席を得られず、小政党Cが3議席目を獲得できる可能性が高くなる。確かに小政党に有利といえるが、民意を反映した選挙結果ではなくなります。
さらに最初のケースで、大政党Aの候補者を3人に変えてみます。すると、大政党Aの候補者と大政党Bの候補者の平均得票率が逆転し、大政党Bに2議席、大政党Aに1議席という可能性が大きくなります。大政党Aによる「票割り」(候補者調整と票の割り当て)の失敗例です。
以上のように、連記投票制の大選挙区制(中選挙区制)は、とても民意を反映した選挙結果をもたらすとはいえません。小政党に有利なケースが生まれたとしても、例えば定数3なら、比較第3党までしか議席は獲得できないでしょう。
太田光征
http://otasa.net/
トラックバック URI : http://kaze.fm/wordpress/wp-trackback.php?p=232