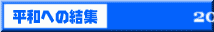小選挙区比例代表連用制
公明党が衆議院選挙制度改定案として提案した小選挙区比例代表連用制について、2009衆議院選挙の結果を基にシミュレーションを行いました。現行定数の場合、小選挙区、比例区いずれかの定数を80削減した場合の3通りです。
議席配分が完全比例代表制とほぼ同じになるのは、小選挙区定数220、比例区定数180の場合、しかもブロック式ではなく全国一括式で比例区議席を割り当てた時のみです。
では、小選挙区定数を削減して小選挙区比例代表連用制にすればよいのかというと、そういうわけにはいきません。
小選挙区と比例区の定数を分離するのが小選挙区比例代表並立制と小選挙区比例代表連用制の本質で、無所属候補と政党候補に同じ総定数をめぐって同じ難易度で競わせる単一の土俵を用意するという思想がまったくない。
小選挙区定数を削減するか、比例区定数を増やした上で小選挙区比例代表連用制に改定すれば、政党にとってはより公平になりますが、無所属・政党間の格差がますます拡大します。
無所属候補(に投票する有権者)は我慢しろ、というのは、一部の人間だけに差別的な放射線被害を負わせても多数が無事であればよい、というのと同じで、認められません。
小選挙区比例代表連用制の小選挙区を中選挙区や大選挙区に置き換えれば、選挙制度思想も結果もずっとマシになるでしょう。
私が提案している中選挙区比例代表併用制は、無所属候補と政党の定数枠を分離するという差別の仕掛けから決別しています。
中選挙区比例代表併用制を提案する
http://kaze.fm/wordpress/?p=164
中選挙区比例代表併用制は、無所属候補、政党候補ともまず同じ総定数をめぐって共通の中選挙区で競わせた上で、無所属候補については中選挙区で議席を確定させ、政党については残余議席を比例配分するというものです。
小選挙区比例代表連用制やドイツの小選挙区比例代表併用制は小選挙区で超過議席を発生させますが、中選挙区比例代表併用制は超過議席を回避できます。
福島原発震災の震源は、過疎地にしか原発を建設してはいけないなどという法律を制定してきた差別政治です。私たちの基幹的・実践的権利を保障する選挙制度がそもそも差別でやられているようでは、今後も私たちは差別政治による政治災害を被り続けることでしょう。
脱原発・国会議員の定数削減・壊憲/原発事故と政党の責任について
http://kaze.fm/wordpress/?p=342
民主党は3・11後、早くも25日の段階で、通常国会で衆議院比例区定数の80削減を実現すると公言しました。悲惨な原発事故被害に遭っている有権者から脱原発政党に投票する1票の価値をさらに減じると宣言したのです。差別に差別の追い打ちをかけるもので、あまりにもひどい。
脱原発は脱差別の運動。脱原発をめぐる攻防は、国会議員の定数削減、選挙制度改定をめぐる攻防と重なっています。震源を揺さぶりましょう。
【目次】
1. 公明党の小選挙区比例代表連用制
2. 小選挙区比例代表連用制のシミュレーション
3. 小選挙区比例代表連用制でも1票格差は解消しない
【関連投稿】
http://kaze.fm/wordpress/?p=309
http://kaze.fm/wordpress/?p=164
1. 公明党の小選挙区比例代表連用制
公明党は衆議院の選挙制度改定案として小選挙区比例代表連用制を提案していますが、これは「政治改革推進協議会(民間政治臨調)」が1993年にすでに提案しているものです。
現在の小選挙区比例代表並立制と小選挙区比例代表連用制の違いは、比例区議席を政党に割り当てる計算方法の違いにあります。
小選挙区比例代表並立制では通常のドント式を採用します。各党の比例区得票数を1、2、3、4、5…という1から始まる整数の除数(比例区での獲得議席数に相当)で割っていき、その商(議員1人当たりの当選に要する得票数に相当)の大きい順に1議席ずつ割り当てるという方法です。
小選挙区比例代表連用制では政党ごとに除数を変えます。各党の除数は、1から始まる整数に小選挙区での獲得議席数を加えた数(小選挙区での獲得議席を比例区で獲得したものとみなす)とし、同様の計算で議席を割り当てていきます。
2. 小選挙区比例代表連用制のシミュレーション
2009年衆議院選挙の結果を基に、大きく3つの条件で、小選挙区比例代表連用制のシミュレーションを行いました。
小選挙区定数を現行の300とし、比例区定数を現行の180とした場合(表1)、民主党が主張しているように比例区定数を80削減して100とし、小選挙区定数を300のままとした場合(表2)、小選挙区定数を80削減して220とし、比例区定数を180のままとした場合(表3)のそれぞれについて、現行の11ブロックごとに比例区議席を割り当てる場合、全国一括で比例区議席を割り当てる場合の結果を計算しています。
小選挙区定数300、比例区定数180の場合(表1)、小選挙区と比例区を合わせた議席数は、小選挙区比例代表並立制と比べて完全比例代表制に近い結果となるものの、民主党では完全比例代表制と比べ26議席(ブロック式)あるいは15議席(全国一括式)も多く獲得しています。この余剰議席は、小選挙区比例代表連用制の欠陥というより、比例区の総定数の少なさ、あるいは定数を細切れにするブロック式に原因があります。
こうした乖離はすでに現在の小選挙区比例代表並立制の比例区選挙でも見られます。
2010参院選――結果分析
http://kaze.fm/wordpress/?p=309
小選挙区定数300、比例区定数100の場合(表2)、民主党は完全比例代表制と比べ53議席も余分に獲得することになります。小選挙区比例代表連用制で比例代表制の側面を強化するのであれば、比例区定数の削減は論外。
小選挙区定数220、比例区定数180の場合(表3)で初めて、全国一括式による議席割り当てが完全比例代表制の場合とほぼ同じになります。ブロック式ではまだ乖離を排除できず、民主党の例では完全比例代表制より10議席多い。
小選挙区比例代表連用制で完全比例代表制に近い結果を出すためには、総定数に占める比例区定数の比重を現在より高めることが前提になります。
3. 小選挙区比例代表連用制でも1票格差は解消しない
小選挙区比例代表連用制も選挙制度思想の土台を欠いた制度であり、現在の矮小化された1票格差論に注意が必要です。
小選挙区比例代表連用制は小選挙区比例代表並立制と同様に、比例区は政党の独占枠なので、無所属候補は比例区から議席を獲得できない。
中小政党には議席を正当に獲得しやすい比例区を確保しておきながら、無所属候補には当選の困難な小選挙区のみしか手当てしないのは、候補者差別、主権者差別です。
1票の価値は生票を投じた有権者にしかなく、死票を投じた有権者にはまったくありません。
複数の選挙区間で有権者1人当たりの議席数を平等にして、生票を投じた有権者の間だけで、しかも複数の選挙区間で同じ生票率の場合だけに1票の価値の平等を実現しても、生票を投じた有権者と死票を投じた有権者の間で1票の平等、主権の平等は成立しない。
選挙制度は主権を保障する制度であって、主権の平等を追求せずに限定的な条件下で1票の不平等のみを解消しようとする選挙制度論は、非常に奇妙。矮小化された1票格差論によって主権格差を拡大させてはいけない。
定数を細切れにするブロック式の比例代表制は、異なる政党に投票した有権者の間で1票格差をもたらす仕掛けであり(同じ1議席を獲得するにも小政党は大政党より多くの得票数が必要)、無所属候補に狭く当選しにくい1人区しか与えない比例代表制は、(準比例代表制とも言われる中選挙区制や大選挙区制の場合と比べ)無所属候補に投票した有権者と、広い比例区で政党に投票した有権者の間で1票格差をもたらす仕掛けです。
現在の小選挙区比例代表並立制において、比例区の削減は格差を拡大させるので問題だが、小選挙区の定数削減であれば問題ない、というわけにはいかない。
小選挙区の定数を削減すれば、比例代表制の比重が高まって政党の間ではより公正になるものの、無所属候補にとっては当選枠が一層狭まることになり、格差を拡大させます。
参議院選挙でも同様で、例えば1人区と5人区では死票率の乖離という1票格差は避けられない。
議員1人の当選に必要な議席数をあらかじめ決めておけば、政党候補、無所属候補の別に関係なく、1票の価値は平等になります。差別の仕掛けを排した選挙制度は原理的に可能なのです。
選挙制度の設計は、これにいかに近づけるか、という問題になります。
差別の解消を試みた選挙制度として提案しているのが、中選挙区比例代表併用制です。
中選挙区比例代表併用制を提案する
http://kaze.fm/wordpress/?p=164
| 民
主 |
自
民 |
公
明 |
共
産 |
社
民 |
み ん な |
国
民 |
日
本 |
大
地 |
改
革 |
幸
福 |
無 所 属 |
計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比 例 区 定 数 一 八 〇 |
現 行 ブ ロ ッ ク 式 |
北海道 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | * | * | * | 2 | * | 0 | - | 8 |
| 東北 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | * | * | * | * | 0 | - | 14 | ||
| 北関東 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 20 | ||
| 南関東 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 22 | ||
| 東京 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 17 | ||
| 北陸信越 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | * | 1 | 0 | * | * | 0 | - | 11 | ||
| 東海 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 21 | ||
| 近畿 | 0 | 11 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | * | * | 0 | - | 29 | ||
| 中国 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | * | 0 | * | * | * | 0 | - | 11 | ||
| 四国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | - | 6 | ||
| 九州 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | * | * | * | 0 | - | 21 | ||
| 計 | 11 | 62 | 49 | 29 | 11 | 14 | 2 | 0 | 2 | * | 0 | - | 180 | ||
| 全国一括式 | 0 | 55 | 51 | 31 | 16 | 17 | 4 | 2 | 2 | * | 2 | - | 180 | ||
| 民
主 |
自
民 |
公
明 |
共
産 |
社
民 |
み ん な |
国
民 |
日
本 |
大
地 |
改
革 |
幸
福 |
無 所 属 |
計 | |||
| 小 選 挙 区 |
議席数 | 221 | 64 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 6 | 300 | |
| 得票率 | 47.4 | 38.7 | 1.1 | 4.2 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | - | 0.1 | 1.5 | 2.8 | - | ||
| 議席占有率 | 73.6 | 21.3 | 0 | 0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | - | 0 | 0 | 2.0 | - | ||
| 民
主 |
自
民 |
公
明 |
共
産 |
社
民 |
み ん な |
国
民 |
日
本 |
大
地 |
改
革 |
幸
福 |
無 所 属 |
計 | |||
| 比 例 区 + 小 選 挙 区 |
2009議席数 | 308 | 119 | 21 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 480 | |
| 同議席占有率 | 64.2 | 24.8 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.0 | - | ||
| 比例区得票率 | 42.4 | 26.7 | 11.5 | 7.0 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | - | - | ||
| 比例区:ブロック式 | 232 | 126 | 49 | 29 | 14 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 480 | ||
| 比例区:全国一括式 | 221 | 119 | 51 | 31 | 19 | 19 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 480 | ||
| 完全比例制 | 206 | 129 | 55 | 34 | 20 | 20 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 480 | ||
| 民
主 |
自
民 |
公
明 |
共
産 |
社
民 |
み ん な |
国
民 |
日
本 |
大
地 |
改
革 |
幸
福 |
無 所 属 |
計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比 例 区 定 数 一 〇 〇 |
現 行 ブ ロ ッ ク 式 |
北海道 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | 1 | * | 0 | - | 4 |
| 東北 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | 0 | - | 8 | ||
| 北関東 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 11 | ||
| 南関東 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 12 | ||
| 東京 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 10 | ||
| 北陸信越 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | * | * | 0 | - | 6 | ||
| 東海 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 12 | ||
| 近畿 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 16 | ||
| 中国 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 | - | 6 | ||
| 四国 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | - | 3 | ||
| 九州 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | * | * | * | 0 | - | 12 | ||
| 計 | 3 | 29 | 34 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | - | 100 | ||
| 全国一括式 | 0 | 17 | 35 | 21 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | * | 2 | - | 180 | ||
| 民
主 |
自
民 |
公
明 |
共
産 |
社
民 |
み ん な |
国
民 |
日
本 |
大
地 |
改
革 |
幸
福 |
無 所 属 |
計 | |||
| 小 選 挙 区 |
議席数 | 221 | 64 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 6 | 300 | |
| 得票率 | 47.4 | 38.7 | 1.1 | 4.2 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | - | 0.1 | 1.5 | 2.8 | - | ||
| 議席占有率 | 73.6 | 21.3 | 0 | 0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | - | 0 | 0 | 2.0 | - | ||
| 民
主 |
自
民 |
公
明 |
共
産 |
社
民 |
み ん な |
国
民 |
日
本 |
大
地 |
改
革 |
幸
福 |
無 所 属 |
計 | |||
| 比 例 区 + 小 選 挙 区 |
2009議席数 | 308 | 119 | 21 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 480 | |
| 同議席占有率 | 64.2 | 24.8 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.0 | - | ||
| 比例区得票率 | 42.4 | 26.7 | 11.5 | 7.0 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | - | - | ||
| 比例区:ブロック式 | 224 | 93 | 34 | 18 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 400 | ||
| 比例区:全国一括式 | 221 | 81 | 35 | 21 | 13 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 400 | ||
| 完全比例制 | 171 | 107 | 46 | 28 | 17 | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 400 | ||
| 民
主 |
自
民 |
公
明 |
共
産 |
社
民 |
み ん な |
国
民 |
日
本 |
大
地 |
改
革 |
幸
福 |
無 所 属 |
計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比 例 区 定 数 一 八 〇 |
現 行 ブ ロ ッ ク 式 |
北海道 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | * | * | * | 2 | * | 0 | - | 8 |
| 東北 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | * | * | * | * | 0 | - | 14 | ||
| 北関東 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 20 | ||
| 南関東 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 22 | ||
| 東京 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 17 | ||
| 北陸信越 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | * | * | 0 | - | 11 | ||
| 東海 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 21 | ||
| 近畿 | 0 | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | * | * | 0 | - | 29 | ||
| 中国 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | * | 0 | * | * | * | 0 | - | 11 | ||
| 四国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | - | 6 | ||
| 九州 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | * | * | * | 0 | - | 21 | ||
| 計 | 19 | 64 | 46 | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | * | 0 | - | 180 | ||
| 全国一括式 | 7 | 59 | 45 | 28 | 15 | 16 | 4 | 2 | 2 | * | 2 | - | 180 | ||
| 民
主 |
自
民 |
公
明 |
共
産 |
社
民 |
み ん な |
国
民 |
日
本 |
大
地 |
改
革 |
幸
福 |
無 所 属 |
計 | |||
| 小 選 挙 区 |
2009議席数x(220/300) | 162 | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 220 | |
| 得票率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 議席占有率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 民
主 |
自
民 |
公
明 |
共
産 |
社
民 |
み ん な |
国
民 |
日
本 |
大
地 |
改
革 |
幸
福 |
無 所 属 |
計 | |||
| 比 例 区 + 小 選 挙 区 |
2009議席数 | 308 | 119 | 21 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 480 | |
| 同議席占有率 | 64.2 | 24.8 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.0 | - | ||
| 比例区得票率 | 42.4 | 26.7 | 11.5 | 7.0 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | - | - | ||
| 比例区:ブロック式 | 181 | 111 | 46 | 24 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
| 比例区:全国一括式 | 169 | 106 | 45 | 28 | 17 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 400 | ||
| 完全比例制 | 171 | 107 | 46 | 28 | 17 | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 400 | ||
太田光征
http://otasa.net/
トラックバック URI : http://kaze.fm/wordpress/wp-trackback.php?p=346