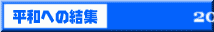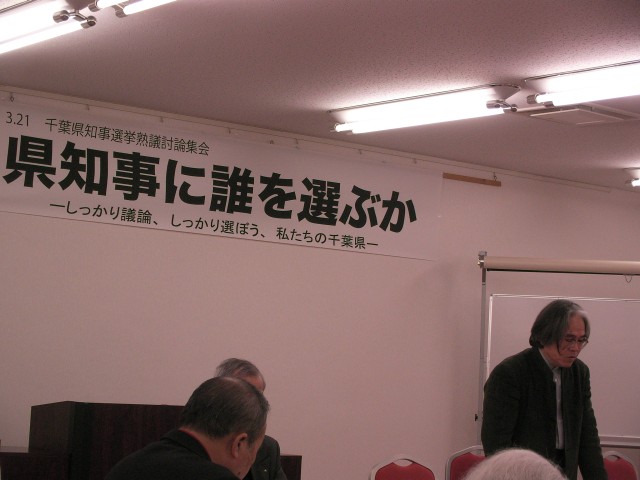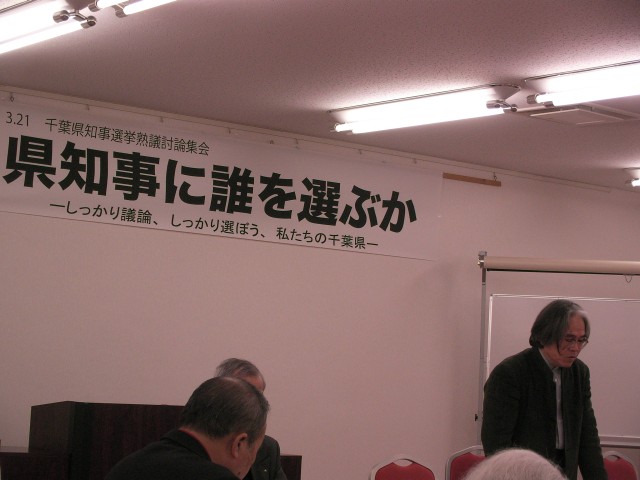
平和への大結集・千葉主催「千葉県知事選挙熟議討論集会」
修正:名前が抜けていたので、追加しました。
(参考)
森田氏:憲法9条は改正を検討すべきである。
(「千葉県知事選ー候補者の政策を知る会」公開アンケート)
【目次】
(1) 主権者はどのような投票行動をすべきか――熟議投票・選挙区すみ分け投票
(2) 千葉県知事選挙熟議討論集会の報告
(3) 「八ッ場ダムをストップさせる千葉の会」公開アンケート
(4) 「千葉県知事選ー候補者の政策を知る会」公開アンケート――鬼泪(きなだ)山からの山砂採取問題など
(5) 浦安合同個人演説会
(6) 朝日新聞 千葉県知事選候補者アンケート
(7) 「平和への大結集・千葉」公開アンケート
(8) 千葉県知事選挙情報サイト
【立候補者】
森田健作氏 無所属 新
八田英之氏 無所属(共産推薦) 新
西尾憲一氏 無所属 新
白石真澄氏 無所属 新
吉田 平氏 無所属(民主、社民、国民新、市民ネット推薦) 新
(1) 主権者はどのような投票行動をすべきか――熟議投票・選挙区すみ分け投票
そもそも「熟議投票」という概念は、小林正弥さんらが2004年参院選に向けて発表したアピールの中で、次のように提案されたものです。
「…選挙制度の変化のために、従来のように政党の支持・不支持だけで投票すると、死票となってしまう危険性が増えています。そこで、現在の選挙制度においては、各党・各候補者の政策に加えて、選挙区の状況を勘案して、投票することが重要になってきています。そこで、『熟議民主主義(deliberative democracy)』の最も重要な一環として、『これらについての情報を得た上で、さらに市民の間で十分な議論を行い、各自で投票を考える』という『熟議投票(deliberative vote)』が望ましいと思います。」
(B−2.「平和への結集」投票の指針:平和を希求する有権者に」
http://mitizane.ll.chiba-u.jp/metadb/up/ReCPAcoe/51kobayashiichinose.pdf)
つまり、小選挙区制という死票を発生させる選挙制度を前提に、候補者の当選可能性なども考慮した戦術的投票のことを熟議投票と呼んでいます。
首長選挙にしろ、議会選挙にしろ、政策をパッケージで提示されたところで、主権者としては一括承認するわけにいきません。選挙で選択できるものには限界があります。
首長や議員の政策決定権限を最小限に抑制し、首長制のあり方について検討し、住民投票制度など、個別課題ごとに民意を直接問う制度を整える必要があるでしょう。
首長選挙は小選挙区制で行うしかありません。そうはいっても、過半数得票率の規定や決戦投票機能などを備えていない現行制度は、コンドルセのパラドックスを考慮していないので、選挙制度の名に値しません。
主権者としては、主権を保障する諸制度の確立にこそ優先的に取り組む必要があります。主権が保障されない枠組みの中で、各政策課題について熟議し、候補者の姿勢を問うことは、いつまでも続けられません。
今回の熟議討論集会では、予想通り、参加者は八田氏(共産党系)を推す人と吉田氏(民主党系)を推す人に分かれました。これでは森田氏の当選を拒むことは難しい。こうした矛盾と対立の構造は、主権を侵害する現行選挙制度に原因があります。
「各自が勝手に投票先を決める熟議投票」だけでは、不十分なのです。各自が勝手に投票先を決められるのは、主権を保障する選挙制度ができてからのこと。それまで主権者は、投票行動を統一する必要があります。
そのような矛盾・対立構造を解消するものとして私が提唱しているのが、「選挙制度修正投票としての選挙区すみ分け投票」です。現行選挙制度では矛盾のない選択などできないのだ、ということを認めなければなりません。そこが出発点です。
熟議討論集会では、首長選挙とその他の選挙をパッケージで考える必要があると提案しました。八田氏側(共産党系)の主権者は、今回は吉田氏側に投票する。その代わり、今度の総選挙の比例区など2人区以上では、吉田氏側(民主党系)が八田氏側(共産党系)に投票する――これで、総体において、私たちが望む平和候補者の当選拡大を図ることができる。
重要なのは、こうした選挙区すみ分け投票によって、民主党に偏っている野党の勢力バランスが修正され、野党共闘路線を確かなものにする効果がある点です。そうした政治力学が生まれて初めて、矛盾に満ちた単純小選挙区制の廃止に道が開かれるでしょう。
選挙区すみ分け投票は、選挙制度改革運動に他ならず、共産党系主権者と民主党系主権者の矛盾・対立構造を解消する機能を持つものです。
(2) 千葉県知事選挙熟議討論集会の報告
平和への大結集・千葉が主催した「千葉県知事選挙熟議討論集会」に参加してきました。
日時:2009年3月21日
会場:千葉市市民会館
主催:平和への大結集・千葉(http://www.xn--x41az7v.jp/~daikessyu/)
参加者から出た意見を簡単にまとめておきます。
―投票率ワースト1は、1981年の千葉県知事選挙で、25.38%。平成9年が28.67%、昭和29年が29.30%、昭和60年が30.7%。
―森田氏は、浦安合同個人演説会では3分の1くらいしか参加していない。残土産廃ネットワークでも公開アンケートをお願いしたが、回答拒否の文面が大結集に対するものとまったく同じで、誠実さが見られない。白石氏からも回答がなかったが、八田氏からは回答をもらった。
―白石氏は、教育政策の見直しを掲げているが、学校選択制とかバウチャー制など、新自由主義的意味での個人の尊重を主張している。
―白石、森田の各氏は、医療の自立を主張。病院ごとの独立採算性のことなら、医療の現実を分かっていない。
―吉田氏は、支持団体を通じて配布するチラシと、一般向けチラシが異なっている。
―市民ネットワーク千葉県の方:市民ネットワーク千葉県は、総選挙に向け、13ある選挙区のうち、6、7選挙区で民主党と政策協定を結んだ。自衛隊の海外派遣には慎重を期することを盛り込んだ。平和・憲法を基準に個人ごとに推薦するかどうかを決めている。吉田氏についても、100%政策を支持しているわけではない。政策協定に、当選後、その都度話し合うという条項をいれてある。
―新社会党の方:新社会党としては、問われれば、八田氏を支持することにしている。吉田氏は、教育基本法の改定推進に立場にあった政治倫理研究会の役員をしている。吉田氏は、教育基本法の改定には賛成しているが、公明党に関する部分には不満だと明言した。吉田氏は、財界も推している。堂本氏は、後に自民党に取り込まれた。吉田氏は、よりまし候補とは言えない。残念だが、当選可能性はないが、八田氏がいいと判断した。
―新社会党の方:8年前、共産党で活動している方から、共産党候補を推す政策協定を持ちかけられたが、共産党県レベルで拒否されたという経緯がある。4年前も、候補者と政策・応援協定を結んだが、チラシに「新社会党支持」という言葉が入った程度で、応援依頼はなかった。
―堂本知事に環境問題で要望をしたが、環境問題は全部自民党が押えていて、何もできないと語っていた。自民党を半分にしてくださいよ、と言われた。堂本氏にとって、手に余る千葉県だった。吉田氏も、有権者が応援しなければならない。知事になったら、(政治を)させること。
―八田氏の周囲がアンケートに回答しなかったことに不信を抱いている。政策についてではなく、自分たちの組織に属さない市民にどう呼びかけて政策を実現していくのか、疑問だ。
―自民党は成田・羽田間に3兆円をつぎ込もうとしている。借金だ。森田氏には30人の自民県議がついている。
―吉田氏が知事選出馬に当たって相談したのが松下政経塾一期生の方だった。当選後にチェックする上でも、候補者の背後を知っておく必要がある。
(3) 「八ッ場ダムをストップさせる千葉の会」公開アンケート
「八ッ場ダムをストップさせる千葉の会」公開アンケート
http://yanbachiba.blog102.fc2.com/blog-category-17.html
八ツ場ダム反対を明確に主張しているのは、八田氏と吉田氏。西尾氏は回答がなかったが、パンフレットなどから、千葉県の財政負担反対は明らか。
白石氏:「八ッ場ダム事業については、治水、利水の観点から事業の必要性は理解できるところであるが、ただ、闇雲に事業を進めるだけでなく、時代のニーズや進め方を検証した上で、事業費の削減など必要な見直しについても考えていくことも必要であると考えている。」
(参考)
白石氏:4600億の事業のうち、すでに7割の執行が完了しており、今後、千葉県の負担金はダム本体工事だけで約46億あり、これを福祉に、という声があるが、千葉県は年間1600億の福祉予算を使っている――という正しい知識を持っていただきたい、と発言。(浦安合同個人演説会)
吉田氏:「千葉県の水需給予測、及び河川整備の点からみて、利水、治水の両面から必要ないと考える。」
森田氏:「この問題は千葉県単独の事業ではないため、関係都県との調整が必要。また全体の建設費が9000億円、千葉県の負担金も780億円に及ぶことから、関係都県と協議、検討した上で対応を考えるべき。」
(4) 「千葉県知事選ー候補者の政策を知る会」公開アンケート――鬼泪(きなだ)山からの山砂採取問題など
「千葉県知事選ー候補者の政策を知る会」公開アンケート
http://chibatiji.exblog.jp/9788796/
鬼泪(きなだ)山周辺の国有林からの山砂採取に明確に反対しているのは、西尾、八田、吉田、森田の各氏。白石氏は、一括文書回答で、その中で鬼泪山に言及していない。
「政策を知る会」公開アンケートではこのほかにも多くの質問項目があり、森田氏が女性関連政策に軒並み否定的な回答をしていることが明白です。
道路・交通についても、リニアモーターカーの導入をすすめると1人回答したのが、森田氏で、「産業の振興、雇用創出のためにも高規格道路(自動車専用道路)づくり(圏央道、第2湾岸、銚子連絡道路など)をすすめる。」を明確に選択したのも森田氏。
(5) 浦安合同個人演説会
浦安合同個人演説会の様子を伝えるJANJANの記事
「千葉県知事選 候補者5氏が揃って演説会」(ビデオあり)
http://www.senkyo.janjan.jp/senkyo_news/0903/0903160494/1.php
以下は、政策に相違が目立つ課題についての発言要旨です。
行財政改革について
西尾氏:県職員に対する地域手当の廃止と聖域のない行政コストのカットを主張。
白石氏:知事報酬の2割カットと県職員の削減、(子育ての終わった)退職間際の職員の給与カット、退職金の半分を県債で支払う、年1千億円カット、法人超過課税の導入で税収増を主張。
森田氏:前年度踏襲主義を止め、事業の見直し等のコスト削減を図る。
八田氏:小泉構造改革と三位一体改革で、仕事が増えたにもかかわらず2008年まで4兆円の税金が減らされたことと沼田県政時代の大型開発が財政破綻の原因。巨大開発の見直しと、福祉型公共事業の転換を主張。
吉田氏:無駄な国直轄事業への財政支出の中止と大胆な投資を主張。
雇用問題について
西尾氏:バイオマスエネルギーの生産や介護事業に力をいれることで雇用を増やす。
森田氏:自分自身の試練を与えられた使命だと思い乗り越えることに頑張ることから入るべきである、頑張ればメシぐらいは食えるのではないかと主張。アクアライン料金を800円に下げて、経済効果を期待する。
八田氏:労働者派遣法の抜本改正を求め、大企業呼び込み型ではない雇用効果の高い福祉型公共事業に転換し、大企業の責任を取らせ、セーフティーネットを拡大する。
吉田氏:企業を倒産させないための緊急融資を県独自の既存制f度を利用して行い、農業ハローワークなどを通じた需要創造を。
白石氏:企業に解雇を思い止まらせるための雇用調整助成金の拡充、失業給付の改善を国に求め、職業教育を進め、成田空港を活かして海外からの渡航者を対象にした遺伝子ビジネスを呼び込みたい。
教育問題について(これ以降、森田氏は退席した)
八田氏:学校間競争と財政支援の格差を持ち込むことになる学力テストの公開には反対し、子供に格差を持ち込まず、生きる力を育てるべき。
吉田氏:学校・家庭・地域が一体となった地域センターによる教育を。
白石氏:出し方に注意をした学力テストの公開に賛成で、成績の悪い学校に人的・資金的資源を投入すべきとし、多様性のある教育と機会均等を主張。学力テストという数値化した実証データで「格差」は測られるし、それに基づき教育を語る必要があるとした。
西尾氏:競争を煽る学力テスト公開には反対で、基本的な生活習慣を身に付けさせることが学力向上につながり、携帯やテレビ、ゲームなど学習を阻害する要因を減らしていくべきと主張。
三番瀬と第二湾岸道路について
白石氏:三番瀬は県独自の保全条例を検討し、湾岸道路は需要予測に基づき検討していきたいとした。
西尾氏:三番瀬は保全しラムサール条約に登録すべきで、第二湾岸には見切りをつけ、湾岸バイパスを。
八田氏:三番瀬のラムサール条登録を急ぎ、第二湾岸道路は財政的重荷であり、慎重にならざるを得ないと主張。
吉田氏:三番瀬はラムサール条約に登録し、アクアライン無料化が実現すれば、湾岸道路は必要なくなるとの見解。
(参考:三番瀬猫実川河口域の埋め立てについて)
森田氏:現段階では明確に判断を下せる段階にはないと考える。今後、様々な意見を伺いながら、検討すべき。
(「千葉県知事選ー候補者の政策を知る会」公開アンケート)
介護問題について
西尾氏:南房総にシニアタウンのようなものを建設したい。
八田氏:千葉県の特別擁護老人ホーム数は全国最低で、これを6000作ると公約。
吉田氏:要介護度4、5の方に対するセーフティーネットを拡大する予算措置が必要であり、在宅やグループホームも検討すべきと主張。
白石氏:後期高齢者医療制度は無理があるので、制度改正を求めていき、介護については、小規模分散型ケアホームを、資金がかかるので、NPOなどを活用して建て、不足する介護士に外国人の活用を検討したいとした。
憲法9条について
回答時に出席していなかった森田氏を除く4名が、1項、2項とも守るべきだとした。
西尾氏:憲法を変えずとも、自衛隊を持つことができたし、将来は非武装を目指すべきと発言。
八田氏:世界の財産が憲法9条、世界で評価が高まっていると主張。
吉田氏:憲法を一切変えないという思想とリンクすることは違うと発言。
白石氏:現憲法下でも自衛隊を持つことができており、国際協力、海外派遣が十分機能していることを改正しない理由に挙げた。
(参考)
森田氏:憲法9条は改正を検討すべきである。
(「千葉県知事選ー候補者の政策を知る会」公開アンケート)
タウンミーティンングについて
八田氏:それを含め様々な機会を捉え様々な意見を聞きたい。
白石氏:堂本氏のようにタウンミーティンングを定例化する考えはない。
西尾氏:膝を付き合わせる会議を設けたい。
吉田氏:(時間切れでコメントなし)
八ツ場ダムについて
白石氏(最後のまとめ演説にて):4600億の事業のうち、すでに7割の執行が完了しており、今後、千葉県の負担金はダム本体工事だけで約46億あり、これを福祉に、という声があるが、千葉県は年間1600億の福祉予算を使っている――という正しい知識を持っていただきたい、と発言。
(6) 朝日新聞 千葉県知事選候補者アンケート
朝日新聞 千葉県知事選候補者アンケート(3月17、18日付)から。
成田空港について
八田氏が、発着回数を際限なく増やすことに反対、森田、白石、吉田の各氏は、年間30万回の発着回数を目指す考え。
医療再生について
森田氏:「自立のための経営サポートや効率化の推進、地域事情に合わせた対策に加えて、自立支援のための資金投入も検討する。」
八田氏:「県が地域医療に責任を果たす姿勢を明確に」
西尾氏:「無駄な公共事業(八ツ場ダム)を直ちに停止・凍結し、この予算を県立医科大学創設に振り向け…」
白石氏:「病院局を地方独立法人化して、七つの県立病院の合理化と自立化を図り、一般会計からの繰り出し金を抑制し、財源を地域医療の中核病院支援へ振り分ける。」
吉田氏:「教養課程修了者を受け入れる4年制の医大を民間と共同で設置するほか、千葉大医学部の定員を増やす。」
(7) 「平和への大結集・千葉」公開アンケート
「平和への大結集・千葉」公開アンケート
http://www.xn--x41az7v.jp/~daikessyu/page012.html
八田氏と森田氏からは文書で回答できない旨、返事がありました。
(8) 千葉県知事選挙情報サイト
下記サイトはニュース記事など情報が豊富です。
千葉県知事選挙2009 千葉を任せていいのは誰なんだ?
http://chibagovernor2009.blog73.fc2.com/
太田光征
http://otasa.net/