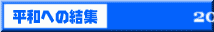2010参院選――結果分析
8月 10th, 2010 Posted by MITSU_OHTA @ 19:51:15under 一般 [85] Comments
2010参院選の結果分析を追々掲載していきます。
【訂正】(2010年12月31日)
表1の定数180で議席配分の計算に間違いがありましたので、訂正します。東北ブロックで自民が1減、みんなが1増、北陸信越ブロックで民主が1増、みんなが1減、四国ブロックで自民が1増、みんなが1減です。それに伴ない、議席占有率も民主が37.2から37.8に、みんなが14.4から13.9に変りましたので、本文も訂正しました。修正した議席配分表ファイルを後日アップします。
【目次】
1. 定数が100に削減された場合の衆院比例区選挙シミュレーション
2. 民意を反映しない中選挙区制
3. 完全比例代表制であれば旧野党は過半数を維持できた
4. 定数削減でも身の切りようがない
1. 定数が100に削減された場合の衆院比例区選挙シミュレーション
まずは、今回の結果に基づいて行った衆院比例区選挙のシミュレーションです。定数180の場合と、定数が100に削減された場合の選挙結果を予想しました。
表1がその結果で、その一部を抜粋した表2を先に掲載しておきます。比例区定数が100に削減された場合の衆院選比例区シミュレーションで指摘したことが再確認できます。
| 民主 | 自民 | 公明 | 共産 | 社民 | みんな | 国民 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票率 | 31.6 | 24.1 | 13.1 | 6.1 | 3.8 | 13.6 | 1.7 |
| 議席占有率 (定数180) |
37.8 | 27.8 | 14.4 | 3.9 | 2.2 | 13.9 | 0 |
| 議席占有率 (定数100) |
41.0 | 29.0 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0 |
| 全国一区議席数 (定数180) |
58 | 44 | 24 | 11 | 7 | 25 | 3 |
| 全国一区議席数 (定数100) |
33 | 25 | 13 | 6 | 4 | 14 | 1 |
| 1票の格差 (定数100) |
1.00 | 1.08 | 1.21 | 3.96 | 4.98 | 1.36 | - |
表2に示したように、民主と自民は現在の定数180でも得をしていますが、定数100ではさらに得をします。特に民主は定数100で議席占有率が得票率より約10ポイント上回るようになり、全国一区の比例代表制と比べて8議席多く獲得できます。
逆に、定数100における共産・社民の議席占有率は、共産が得票率の約3分の1、社民が得票率の約4分の1となります。
比例代表制といっても現在の定数ですら名ばかりで、定数100に削減されることで比較大政党と比較小政党の格差が一層拡大するということです。1票の格差(当選議員1人当たりの得票数)は民主と社民の間で4.98倍となります。
格差は比較大政党と比較小政党の間だけに限りません。現行定数180でも、みんなの党と公明党のように得票率が互角の比較中政党の間でおかしな格差が発生します。公明対みんなの予想議席数は定数180で26対25、定数100で14対13となり、得票率で公明を上回るみんなが、議席占有率で公明を下回るという事態が発生するのです。
定数100に削減されると、この格差はわずかな得票数の変化で拡大し得ます。特に北海道ブロックと四国ブロックで公明が数万票を上積みすればさらに2議席を獲得して、得票率ではみんなを下回ったまま、16対13と議席数でみんなを上回るでしょう。
得票率と議席占有率の逆転現象はなぜ発生するのか。南関東ブロックで説明しましょう。みんなの得票率は公明の1.33倍あるので、本来であれば議席割当は公明3に対してみんな4という割合になるはずです。実際、定数180ではそうした割り当てになっています。ところが総定数100では南ブロックの定数がわずか12と少ないために、公明2、みんな2という割合になってしまうのです。北関東ブロックも同様に、定数が少ないが故にみんなが応分の議席を獲得できない。こうした理由で不利になるブロックがみんなの側に多いために、逆転現象が発生します。総定数100であっても全国一区であればこうした逆転現象は起こりません(表1)。
比例区定数の削減は単なる定数削減ではなく、選挙制度の改定そのものであり、無駄削減というすりかえで選挙制度を改定することは許されません。
比例区定数100でも共産・社民はそれぞれ2議席、1議席を獲得できるという予想ですが、新党日本と新党大地が立候補していない今回の参院選の結果を前提にしています。新党日本が次期衆院選に立てば共産・社民の議席を相当奪うと予想されるので、共産・社民の議席獲得は危うくなるでしょう。共産は東京の議席を自民に、近畿の議席をみんなに、社民は九州の議席を民主に奪われる可能性が大です(議席配分表参照)。
| 民 主 |
自 民 |
公 明 |
共 産 |
社 民 |
み ん な |
国 民 |
た ち 日 |
改 革 |
創 新 |
女 性 |
幸 福 |
計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 数 一 〇 〇 |
ブ ロ ッ ク 式 |
北海道 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 東北 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 北関東 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 南関東 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 東京 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 北陸信越 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 東海 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 近畿 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 中国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 四国 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 九州 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 計 | 41 | 29 | 14 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 議席占有率 | 41 | 29 | 14 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 得票率 | 31.6 [42.4] (39.5) |
24.1 [26.7] (28.1) |
13.1 [11.5] (13.2) |
6.1 [7.0] (7.5) |
3.8 [4.3] (4.5) |
13.6 [4.3] (-) |
1.7 [1.7] (3.0) |
2.1 [-] (-) |
2.0 [0.1] (-) |
0.8 [-] (-) |
0.7 [-] (-) |
0.4 [0.7] (-) |
- | ||
| 得票率x定数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 全国一括式 | 33 | 25 | 13 | 6 | 4 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 民 主 |
自 民 |
公 明 |
共 産 |
社 民 |
み ん な |
国 民 |
た ち 日 |
改 革 |
創 新 |
女 性 |
幸 福 |
計 | |||
| 定 数 一 八 〇 |
ブ ロ ッ ク 式 |
北海道 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 東北 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 北関東 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 南関東 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 東京 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 北陸信越 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 東海 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 近畿 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 中国 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 四国 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 九州 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 計 | 68 [87] (85) |
50 [55] (55) |
26 [21] (25) |
7 [9] (10) |
4 [4] (4) |
25 [3] (-) |
0 [0] (0) |
0 [-] (-) |
0 [0] (-) |
0 [-] (-) |
0 [-] (0) |
0 [0] (-) |
180 | ||
| 議席占有率 | 37.8 | 27.8 | 14.4 | 3.9 | 2.2 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 得票率 | 31.6 [42.4] (39.5) |
24.1 [26.7] (28.1) |
13.1 [11.5] (13.2) |
6.1 [7.0] (7.5) |
3.8 [4.3] (4.5) |
13.6 [4.3] (-) |
1.7 [1.7] (3.0) |
2.1 [-] (-) |
2.0 [0.1] (-) |
0.8 [-] (-) |
0.7 [-] (-) |
0.4 [0.7] (-) |
- | ||
| 得票率x定数 | 56.8 | 43.3 | 23.5 | 11.0 | 6.9 | 24.5 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | - | ||
| 全国一括式 | 58 | 44 | 24 | 11 | 7 | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 180 | ||
今回の参院選は小選挙区制とともに中選挙区制の弊害をよく示しています。民主は議席数で「惨敗」したとはいえ、比例区だけでなく選挙区全体でも得票率で自民を上回っているのです(表3)。民主が得票率で負けているのは1人区のみです。
民主は3人区と5人区で得票率と議席占有率がよく一致しているのに対して、自民は1人区以外でも、2人区から5人区のすべてで議席占有率が得票率を大きく上回りました。
2人区から5人区で、自民は得票率で民主より約12ポイント負け越しているものの、議席数では2議席、議席占有率では約5ポイントしか負け越していません。
これは、比例代表制に近い結果を出すと言われる中選挙区制が実際にはそうでないことを示しています。
2人区は、得票率に大きな開きがあっても第一党と第二党で議席を等しく山分けする論外の制度になっています。3人区も2割台の得票率で3割の議席、5人区も1割台の得票率で2割の議席を獲得できる仕掛けです。
公明が比例代表制ではなく中選挙区制を主張している理由はそこにあるのでしょう。公明は比例区得票率が13.07%ですが、5人区では得票率13.20%で1議席(20.00%)を獲得しています。定数5の中選挙区なら、公明は議席占有率で約7ポイント得をするわけです。公明は2009東京都議会議員選挙でも2人区から8人区すべてで議席占有率が得票率を上回っています。
| 民主 | 自民 | 公明 | 共産 | 社民 | みんな | 候補者計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人区 | 得票数 | 6,659,286 | 8,251,162 | - | 1,143,783 | 78,792 | 681,995 | 17,598,183 |
| 議席数 | 8 | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 得票率 | 37.84 [47.43] (36.56) |
46.89 [38.68] (42.56)(民主との直接対決区に限ると30.57) |
- | 6.50 | 0.45 | 3.88 | 100.00 | |
| 議席占有率 | 27.59 | 72.41 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2人区 | 得票数 | 7,402,098 | 6,062,468 | - | 1,324,796 | 51,463 | 2,039,141 | 17,848,950 |
| 議席数 | 12 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 得票率 | 41.47 | 33.97 | - | 7.42 | 0.29 | 11.42 | 100.00 | |
| 議席占有率 | 50.00 | 50.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 3人区 | 得票数 | 6,287,210 | 4,171,939 | 1,458,956 | 1,235,634 | 376,744 | 2,600,226 | 16,855,907 |
| 議席数 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| 得票率 | 37.30 | 24.75 | 8.66 | 7.33 | 2.24 | 15.43 | 100.00 | |
| 議席占有率 | 40.00 | 33.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 100.00 | |
| 5人区 | 得票数 | 2,407,406 | 1,010,514 | 806,862 | 552,187 | 95,685 | 656,029 | 6,097,767 |
| 議席数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 得票率 | 39.50 | 16.60 | 13.20 | 9.10 | 1.60 | 10.80 | 100.00 | |
| 議席占有率 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | |
| 2 | 5人区 |
得票数 | 16,096,714 | 11,244,921 | 2,265,818 | 3,112,617 | 523,892 | 5,295,396 | 40,802,624 |
| 議席数 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | |
| 得票率 | 39.45 | 27.56 | 5.55 | 7.63 | 1.28 | 12.98 | 100.00 | |
| 議席占有率 | 45.45 | 40.91 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 100.00 | |
| 選挙区計 | 得票数 | 22,756,000 | 19,496,083 | 2,265,818 | 4,256,400 | 602,684 | 5,977,391 | 58,400,807 |
| 議席数 | 28 | 39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | |
| 得票率 | 38.97 | 33.38 | 3.88 | 7.29 | 1.03 | 10.24 | 100.00 | |
| 議席占有率 | 38.36 | 53.42 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 100.00 | |
| 比例区 | 得票数 | 18,450,140 | 14,071,671 | 7,639,432 | 3,563,557 | 2,242,736 | 7,943,650 | 58,453,437 |
| 議席数 | 16 | 12 | 6 | 3 | 2 | 7 | 48 | |
| 得票率 | 31.56 | 24.07 | 13.07 | 6.10 | 3.84 | 13.59 | 100.00 | |
| 議席占有率 | 33.33 | 25.00 | 12.50 | 6.25 | 4.17 | 14.58 | 100.00 | |
| 選挙区 + 比例区 | 議席数 | 44 | 51 | 9 | 3 | 2 | 10 | 121 |
| 議席占有率 | 36.36 | 42.15 | 7.44 | 2.48 | 1.65 | 8.26 | 100.00 |
全国一区の完全比例代表制であれば、自民はたったの30議席、民主は4減の40議席となり、民主・共産・社民・国民全体で53議席となります(表4)。2007参院選で同様に計算してみると、民主・共産・社民・国民・新日全体で69議席なので(議席配分表参照)、同制度であれば旧野党はちょうど過半数の122議席を維持できたわけです。
2007参院選では旧野党系の無所属候補がかなり当選しました。中選挙区比例代表併用制のように、無所属候補を当選させた上で、総定数の残りに比例代表制を適用して政党に議席を配分する方式で計算してみると、無所属全体が計7議席で、うち旧野党系が5議席、民主・共産・社民・国民・新日全体が65議席だから、旧野党系全体は70議席となり(議席配分表参照)、やはり旧野党系が今回の参院選の結果(無所属の当選がゼロなので53議席)と合わせて過半数を維持できたことになります。
| 民 主 |
自 民 |
公 明 |
共 産 |
社 民 |
み ん な |
国 民 |
た ち 日 |
改 革 |
創 新 |
女 性 |
幸 福 |
計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全比例代表制 | 議席数 | 40 | 30 | 16 | 7 | 4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 121 |
| 議席占有率 | 33.06 | 24.79 | 13.22 | 5.79 | 3.31 | 14.05 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.83 | 0 | 0 | - | |
| 現行比例区得票率 | 31.56 | 24.07 | 13.07 | 6.10 | 3.84 | 13.59 | 1.71 | 2.11 | 2.01 | 0.84 | 0.71 | 0.39 | - | |
「国会議員」はしきりに身を切りたがっています。消費税増税などの負担を国民に求めるのであれば、国会議員自ら身を切る必要があり、なぜかそれが国会議員定数を削減することなのだといいます。
(国会議員の定数削減について)「まず議員が自ら身を切る姿勢で、できるだけ年内に実現できるテンポで議論を進めてほしい」(菅直人首相、 8月2日、衆院予算委員会)
「『国民に負担を求める前に、まずは国会議員や官僚が身を切るべきだ』との国民の声に真摯に応えていく決意」(みんなの党2010選挙公約)
「年金、医療、介護の抜本改革の財源として消費税を否定しないが、物事に は順番がある。国民にお願いする以上、まずはわれわれ国会議員の定数を思い切って削減していく」(樽床伸二民主党国会対策委員長、7月6日、松山市の街頭演説)
「隗より始めよ、自分たちの身を切ることなしに全てのことは始まらない」(樽床伸二民主党国会対策委員長、7月6日、埼玉県さいたま市内の集会)
消費税の負担ごときで身を切る必要があるなら、沖縄に米軍基地の負担を押し付けておいて平気でいられるはずはありません。切腹したいのではないでしょうか。
しかし、菅直人首相は6月11日の所信表明演説で「沖縄を襲った悲惨な過去に思いをいたすとともに、長年の過重な負担に対する感謝の念を深めることから」と述べ、身を切るどころの覚悟ではありません。この落差は沖縄に対する差別とともに、「身切り論」がまやかしであることを示しています。
そもそも、定数削減で比較大政党の現職議員が身を切ることはありません。
今回の参院選では新人が55人も当選しました。2007参院選でも新人当選者は65人ですから、現在の参院は計120人の新人議員がいることになります。2009衆院選でも新人当選者は158人もいます。従って新人は衆参計で278人となり、総定数の38.5%を占めます。
選挙ごとに新人議員の当選者数は異なるでしょうが、この278人、38.5%が一応の目安となるでしょう。
自民公約のように衆参で計3割削減したとしても、新人の擁立者数を減らせばよいだけだから、比較大政党の現職議員が身を切ることはないのです。
衆院で180議席、参院で142議席減らすというみんなの党の案なら身を切ることも可能でしょうが、新党改革の半減案とともに正気の沙汰ではありません。
参院の第一種常任委員会は計11あり、議員は複数の委員会を掛け持ちできません。みんなの党の案に従って定数が242から100となれば、各委員会の定数はわずか9人前後となります。
さらに、定数削減で小政党の議席が減少すれば、小政党が参加できない委員会の数は一層増加します。これでは民意を反映したまともな委員会審議などできません。
定数削減という身切り論に国会の民主主義機能を向上させるなどという発想はまったくなく、勢力が弱小な政党ほど多くの削減数を主張して人気取りを図り、保守比較大政党以外の比較小政党を排除しようとしているだけです。
身を切られるのは比較小政党であり主権者です。敵対党と主権者の身を切るから消費税を上げさせてくれという理屈は成り立ちません。
太田光征
http://otasa.net/
トラックバック URI : http://kaze.fm/wordpress/wp-trackback.php?p=309